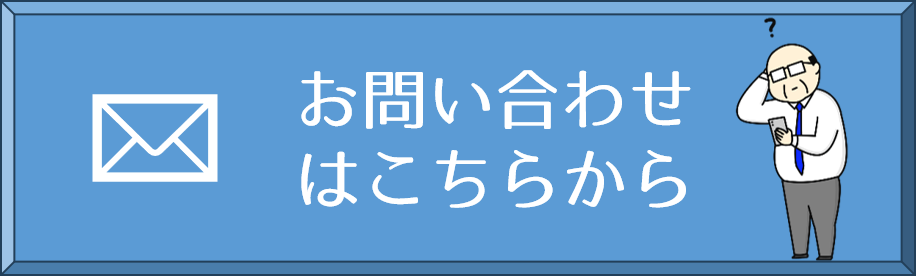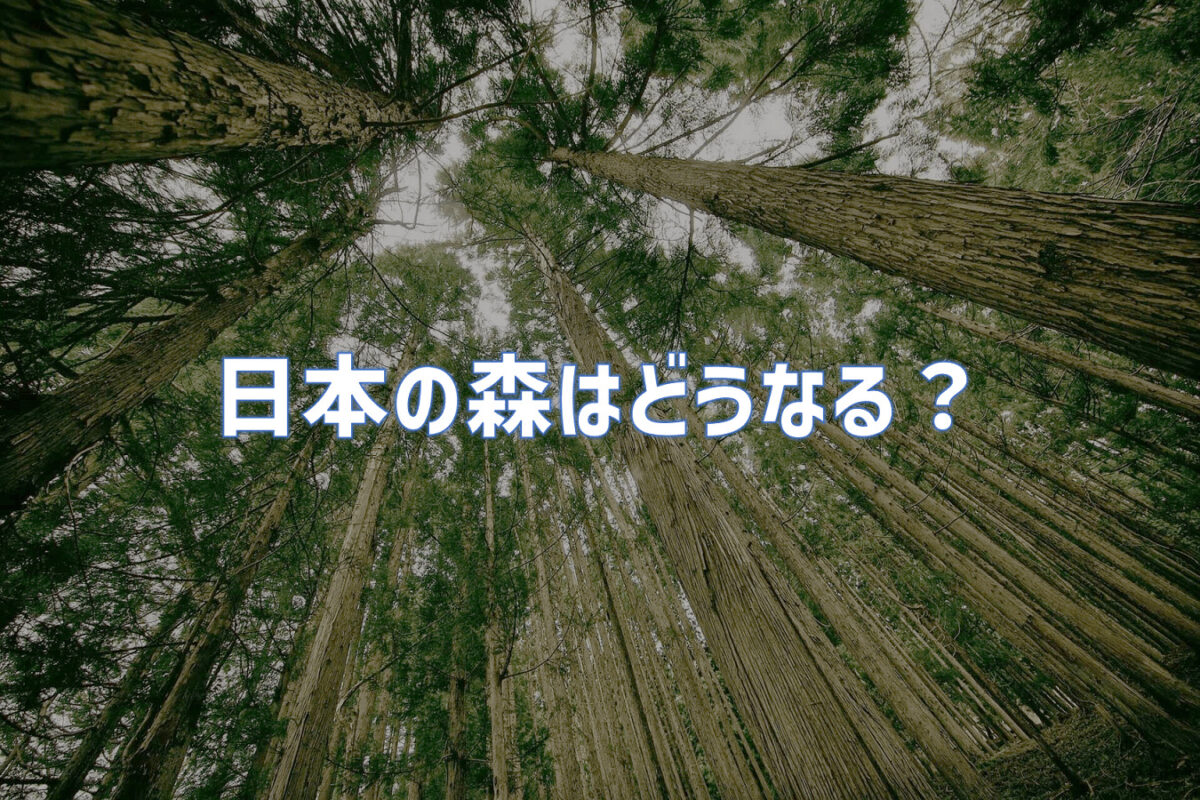
2020年の世界の森林面積は4,058,931,000haで、地球の陸地面積の約27.6%を占めています。
ちなみに地球の陸地面積は、昔学校で習いましたよね?!
147,244,000km²で地球の面積の約28.9%です。
海は362,822,000km²の71.1%です。
一般的には29対71って言います。いや、3対7かな?
話を戻して、世界の森林面積は1990-2020年の30年間で1億7800万ha減少しました。
これは、日本の国土面積の約5倍の面積です。
一方で中国は大規模な植林を行っていて、年1,937,000haもの森林面積が増加しています。
2位のオーストラリアですら446,000haの増加ですから、中国はすごい頑張ってますよね。
逆にブラジルでは1,496,000ha、コンゴ民主共和国では1,101,000haもの森林面積が一年で消失しています。
植林などで森林面積が増えているものの、熱帯雨林を中心に伐採が進み、森林面積の減少に歯止めがかかっていません。
日本の森林面積は、24,935,000haで森林率は68.4%です。
OECD加盟国だと3位です。ちなみ1位はフィンランドで73.7%、2位はスウェーデンで68.7%です。
世界的な森林の減少は、地球温暖化や生物多様性の喪失、砂漠化などを進行させ、地球規模での環境問題をいっそう深刻化させています。
日本の林業
日本の森林の現状を一言で表すとすれば「荒廃」でしょう。
かつて森林は、私たちの生活に密着していました。木材で家を建て、家具や器具を作るとともに、燃料となる薪や炭、山菜やきのこ、落ち葉など、豊かな資源を活用しながら森林を育んできました。
しかし、私たちの生活が変化し、森林との関わりが少なくなるとともに、手入れが遅れ、荒れていく森林も増えています。
きっと、この記事を書いている10年後、2031年には、農業や林業を生業としている人はほぼ壊滅しているものと思います。
そうなっていなければ、予想が外れたけど良かったと言えます。
働き世代の人は、きっと椅子に座ってパソコンに向かい、仕事をしている人がほとんどでしょう。
IT化の名のもと、便利で快適な生活を送ることを追い求めているはずです。
将来、食べ物を育てる農業、水を育む林業に従事している人は存在するのでしょうか。
人間が生きていくうえで根幹となる部分の仕事をしている人が、存在しているのでしょうか。
スーパーやコンビニに行けば、食べる物は当たり前のように並んでいます。蛇口をひねれば当たり前のように飲める水が出てきます。
それが出来なくなった時、どれだけIT化が進み便利で快適な世の中になったとしてもまったく意味がありません。
極論を言えば、電気がなくても人間は生きていけます。車がなくても生きていけます。
最も大切なのは、食べるものがあるということと、飲める水があるということではないのでしょうか。

森づくり
森づくりをしないといけない森林は、「人工林」と「天然林(雑木林)」です。
人工林とは、人が苗を植えて育てている森林のことです。
森林面積の約4割を占める人工林のかなりの部分は、第二次世界大戦後に植えられたスギやヒノキなどの針葉樹です。
国内の主要都市が空爆で焼かれてしまい、戦後の復興に大量の木材が必要となりました。
各地の森林からたくさんの木が伐採されましたが、木材が不足したうえ価格も高かったことから、全国各地で雑木林をスギやヒノキ、カラマツなど比較的成長が早い針葉樹が植えられたのです。
戦後に植えられた木は、順調に育っていきましたが、昭和39年に木材の輸入が自由化され、外国材が大量に輸入され始め、国産材は見向きもされなくなり放置されていったのです。
私が子どもの頃は花粉症なんて病気はありませんでしたが、今では春の風物詩です。
私が子どもの頃にたくさん植えられたスギやヒノキの木が放置されている影響なのかもしれません。
人工林が放置されている理由はただ一つです。「木材価格の下落」だと言えます。
天然林(雑木林)とは、伐採などにより人間の影響を受けているが、自然状態で回復した森林のことです。
クヌギやコナラなどの落葉広葉樹、シイやカシなどの常緑広葉樹の森林です。切り株から芽が出て再生する性質(萌芽更新)をいかして利用してきた森林です。
この雑木林が放置されている原因は、燃料革命でしょう。
薪や炭に変わり、ガスや石油が使われるようになったからです。
森林は農業と違って、ほったらかしにしても木が成長するという一面もありますが、人の手で植えられた人工林となるとそうはいきません。
枝打ちをしたり間伐をしたり手入れをしないと、経済的に価値のある木材となる木は育ちません。
そう、人工林の手入れをする理由は、価値の高い木を育てるためです。
では、天然林(雑木林)の手入れは何のために行うのでしょうか。
それは、ずばり健康な森を育てるためです。
私たちは都市の中に住んでいると、森林のことは忘れてしまいがちです。
森林があるおかげで、私たちは安全で快適に暮らすことができます。
どんなにITが進化し、便利な世の中になったとしても、健康な森林がなくなると快適な暮らしは遠ざかっていきます。
毎年のように災害が発生し、水不足に悩み、汚れた空気の中、薄い酸素の中で生きていくことが快適と言えるのでしょうか?

日本の国立公園
最後に、日本の国立公園の話です。
というのも、最近まで国立公園の名前は知っていましたが、あまりに禁止事項が多い事実を知ったのでここで紹介します。
まあ、禁止事項が多いのは、日本の優れた自然の風景地を保護し、生物多様性を確保するためなので、当然と言えば当然のこと。
日本の国立公園は、土地の所有にかかわらず公園を指定できる「地域制自然公園制度」を採用しています。
私は行政にいた人間ですから、都市公園なんかを整備していましたが、それらの土地の権原はすべて公でした。つまり、民有地であれば土地を購入する必要がありました。
この自然公園は、民有地でも公園を指定できるとは知りませんでした。
そんな公園制度があるんだと思いました。
というのも、規制を守ってもらうのが大変そうというのがあるからです。
土地や建物を所有している人は、自分の権利を主張するのではとの思いがあります。
なので、管理監督が大変そうです。
日本の国立公園は、大きく分けて5つの保護区分で事業行為などを規制しています。
最も厳しいのが「特別保護区域」で、すべての動植物の捕獲・採取、植物の植栽、種をまくこと、家畜の放牧、焚火などは許可が必要で、事実上「禁止」されています。
ちなみに落葉落枝の採取も禁止です。落ち葉の一枚くらいと思うかもしれませんが、ダメです。
宮島にもよく行きますが、弥山の山頂付近はこの特別保護区域です。
落葉の一枚でも拾ったらダメです。
でも、よく落ち葉の掃除をしている人を目にするんです。
これは大丈夫なのかな?と思うところですが、きっと役所から委託されて綺麗にしているのでしょう。これも観光地の宿命なのかな?
国が落ち葉の一枚でも拾ったらダメといいつつ、市が美化のためにと落ち葉を拾い集めている。
なんて矛盾した島なのかと思ってしまった所存です。
本当に自然を守りたいのか?と思ってしまいました。
私はよく山に登りますが、山によっては「希少な動植物が存在するので獲ってはいけません。」と大きな看板をあちこちに設置しています。
これ、本気で守りたいのか?といつも思うんですが、本気で守りたいのであれば入山禁止にすればいいのにと思ってしまいます。
観光地として多くの人に来てもらいたいとの思惑が隠れているようにしか思えない今日この頃です。