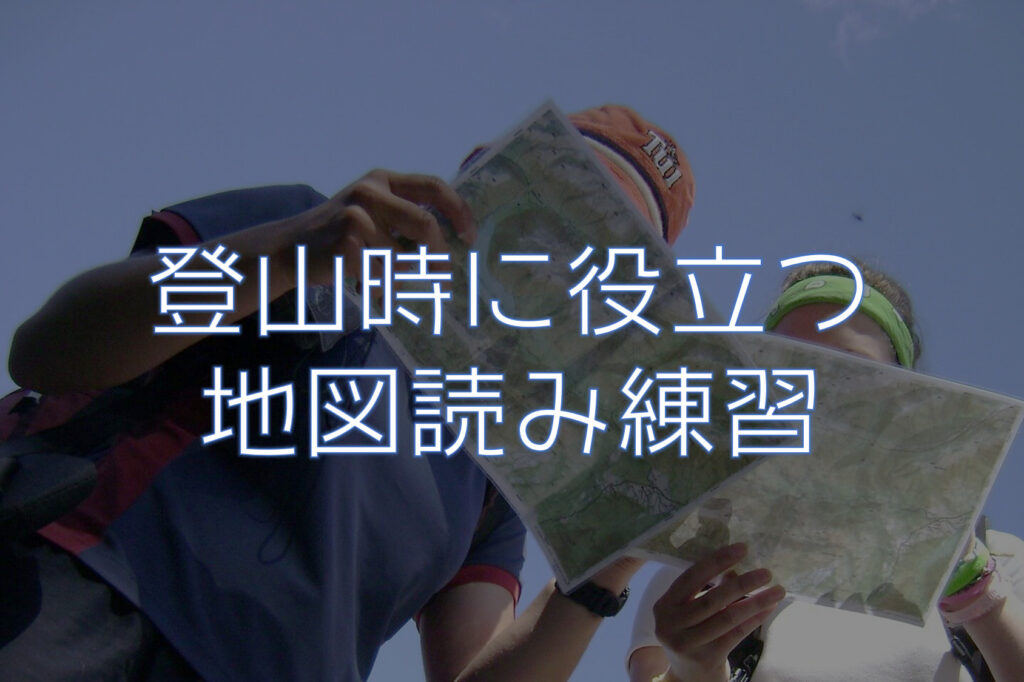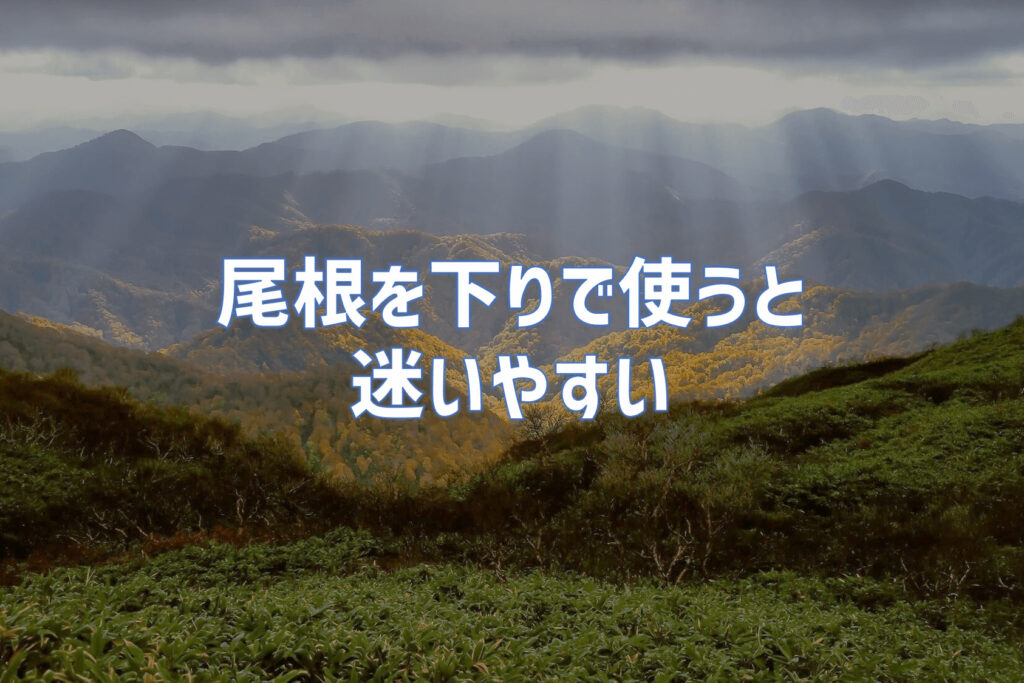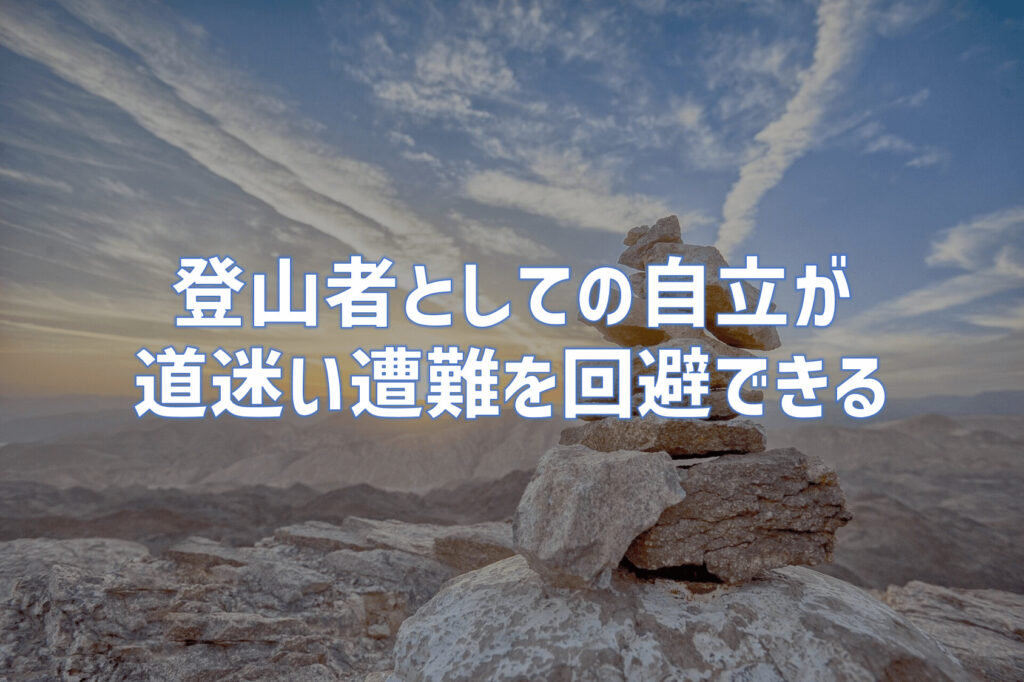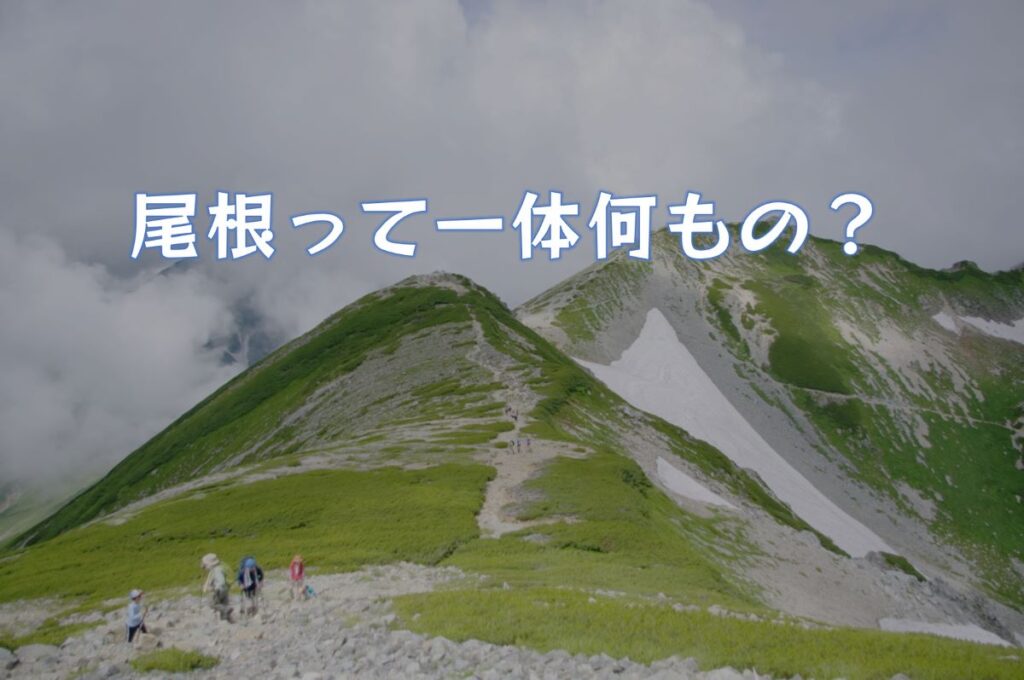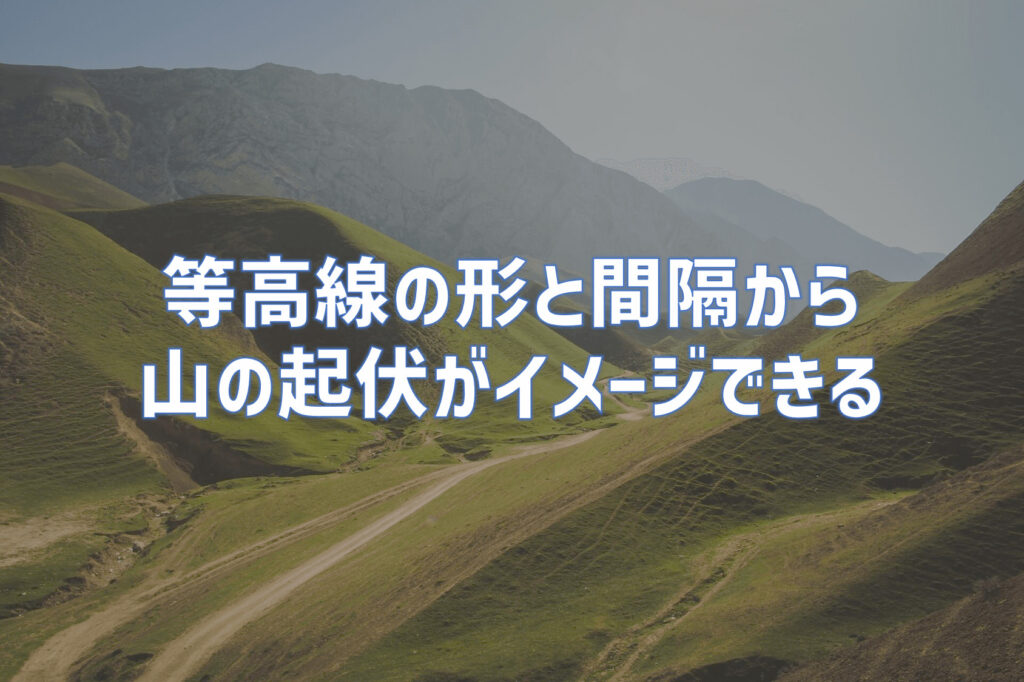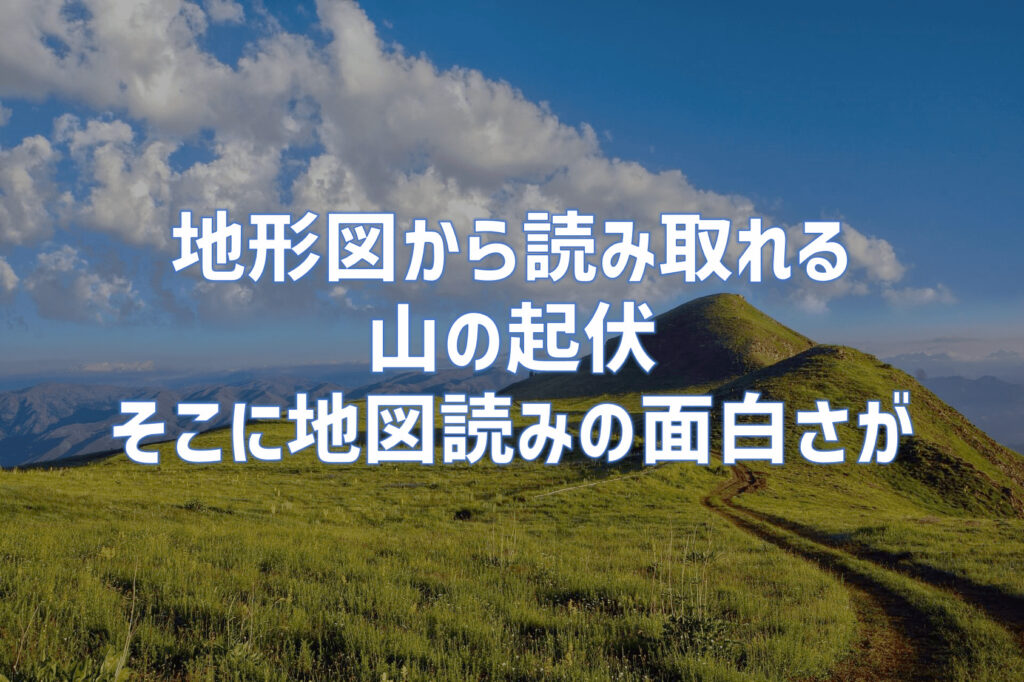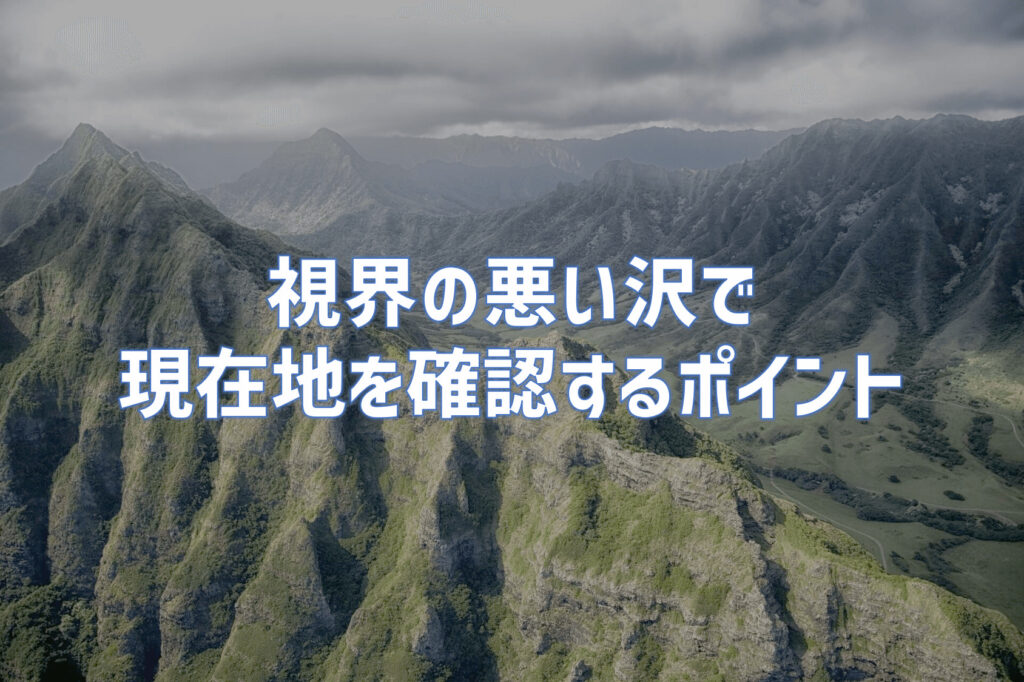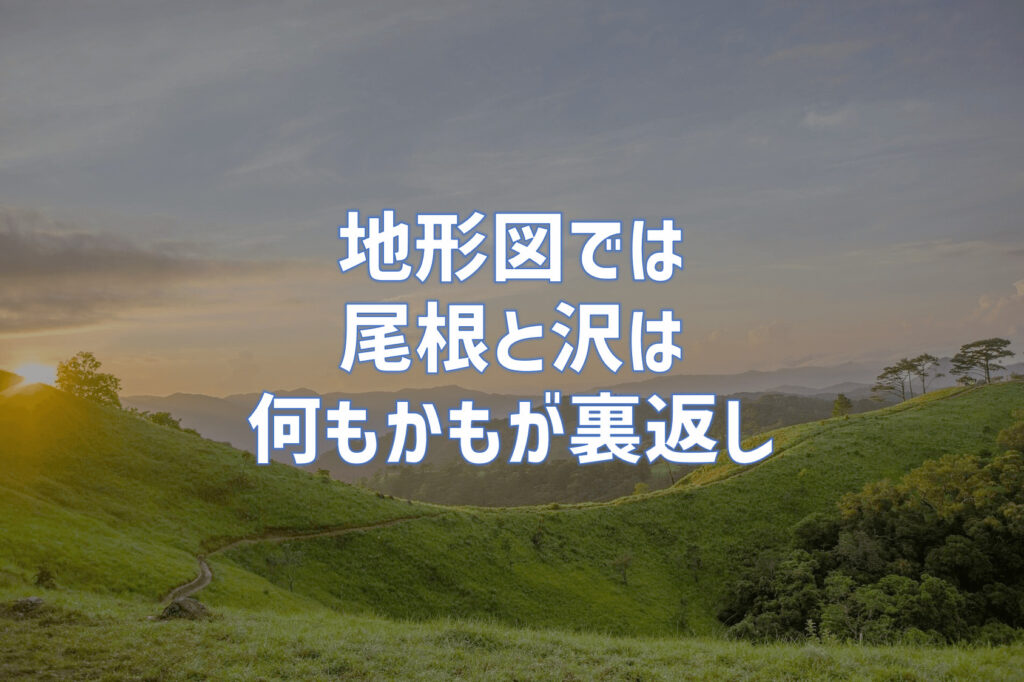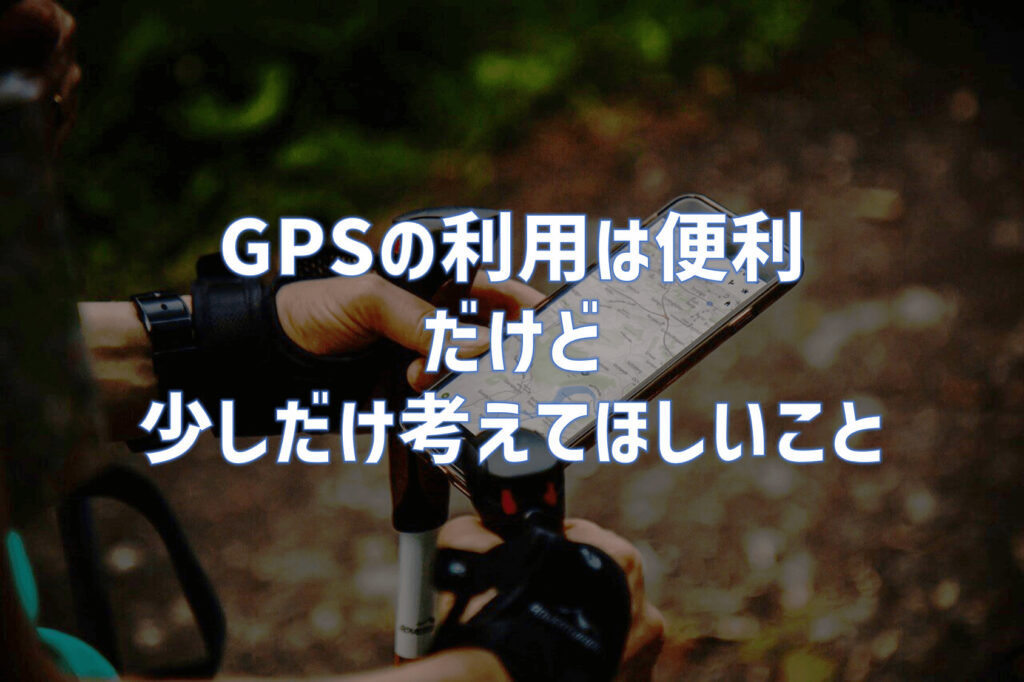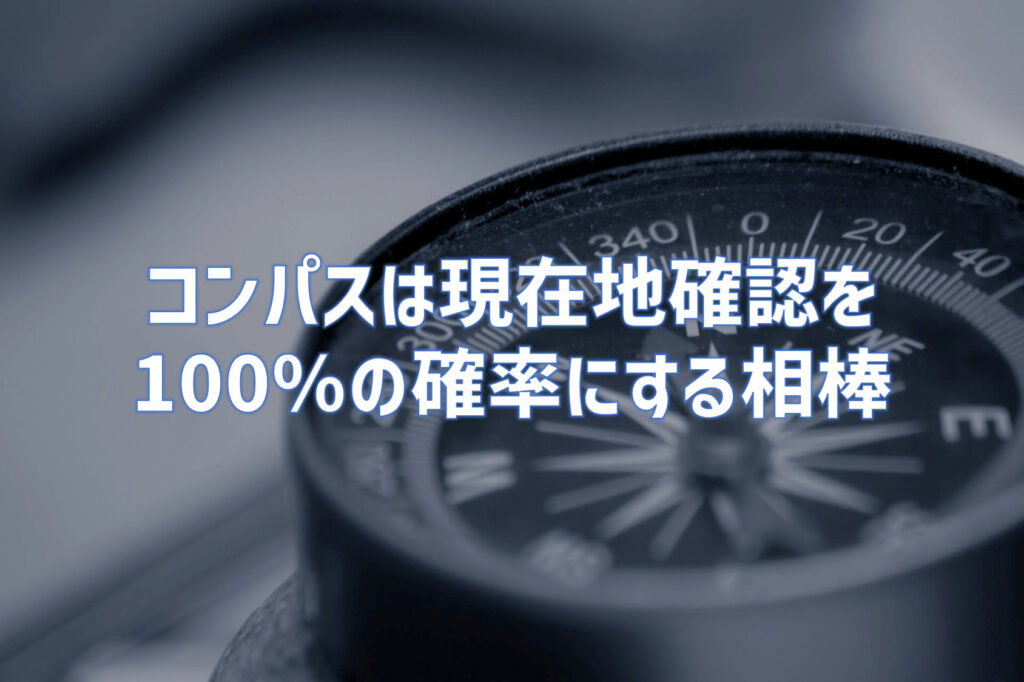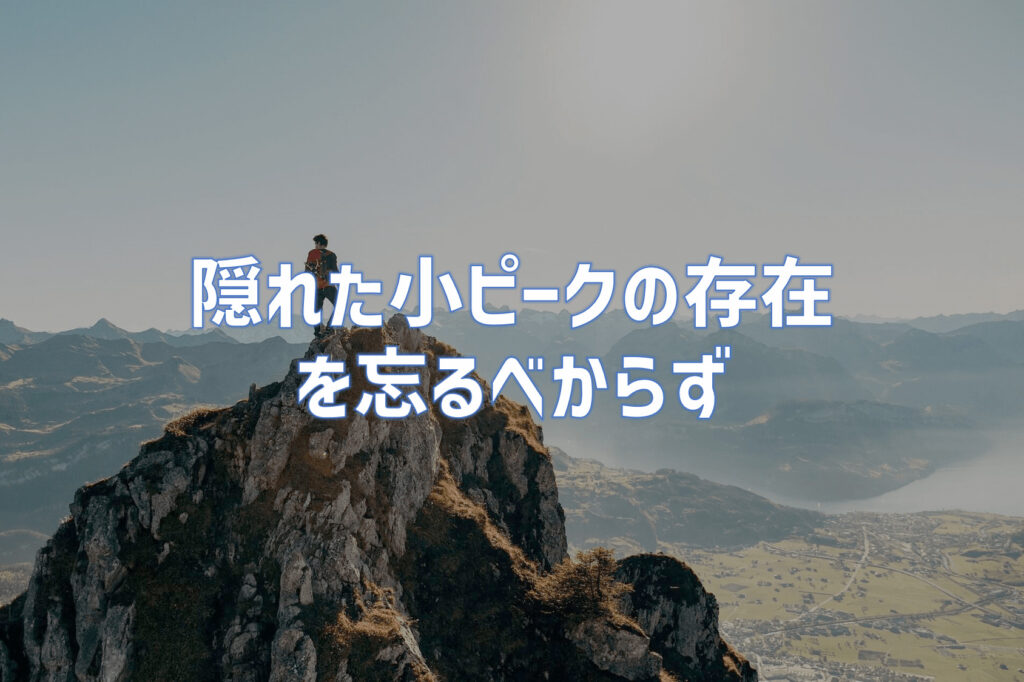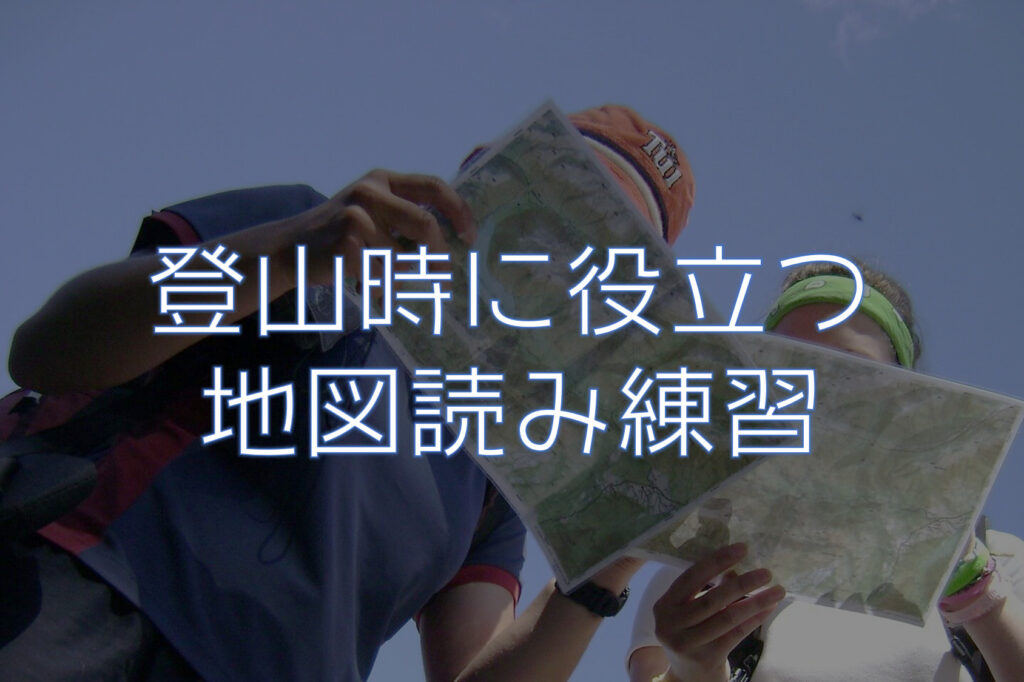
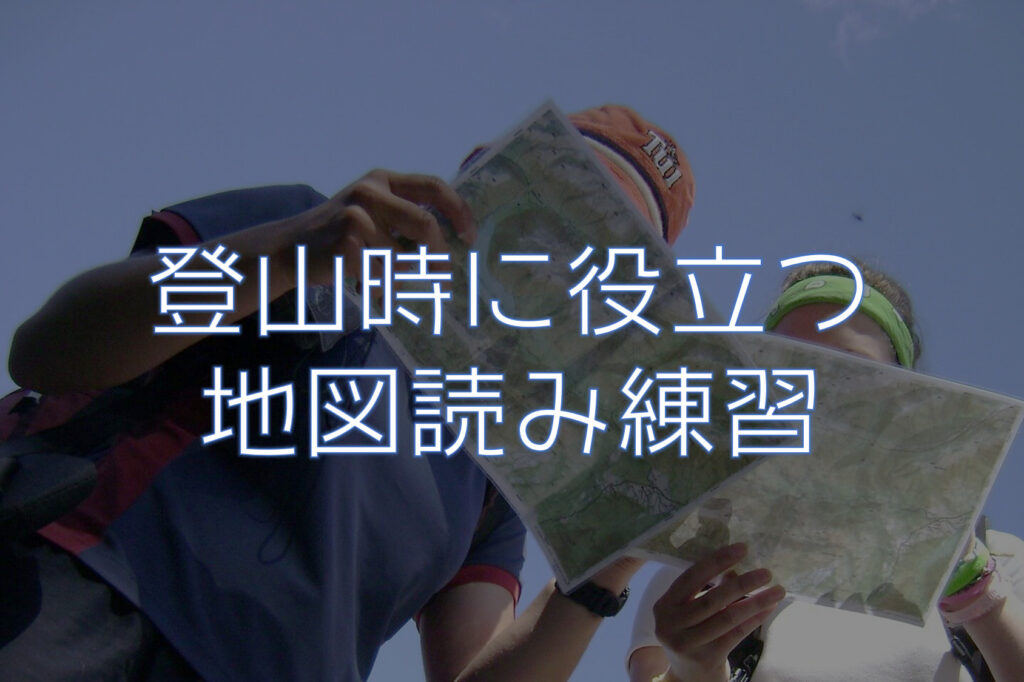
読図は、低山登山においては最も重要なスキルだと個人的には思っています。
ある程度高い山は、登山関係者が多く入山するためなのか迷うような踏み跡が少なく、道標もしっかり整備されています。
これが低山になると状況は一変。
林業や電力事業、地元の人たちが山に入ることが多く、その人たちが付ける明瞭な踏み跡が多く存在しているのです。
さらに、道標もあまり整備されていないために迷う分岐があちこちに。
そう、低山は道迷いのリスクが高いのです。
山での遭難事故の原因は、道迷いがダントツの1位です。
そのリスクを低減するためには、自分は地図上のどこにいて、どこに向かおうとしているのかを知っておくことが重要です。
それは、これから歩く道はどんな道で、次の現在地把握ポイントはどこかといった地図の先読みを繰り返しながら歩くことが重要です。
GPSで現在地の事後報告を受けながら歩くことではありません。
そして、道迷いを遭難に繋げないことが何よりも重要です。
道迷いは誰にでも起こりうるもの。その道迷いに気が付いたら、来た道を引き返すことが重要です。
道迷いに気が付いたとき、誰もが引き返す労力が大きいと勝手にバイアスが働きます。
「この道を引き返さないといけないのか」と誰もが引き返す労力の方が大きいと判断してしまうのです。
ある程度地図が読めるようになると、地図を見て「このまま進んでも大丈夫、ここに下山できる」「この谷を横切れば正規の登山道に戻れる」と考えてしまいます。引き返す労力より小さいと勝手に思い込んでいるのです。
その先に待ち受けるのが滑落や遭難です。首尾よく下山できたとしても、それは引き返すより大きな労力を払っていることでしょう。
道に迷ったと思ったら、来た道を引き返す。これが鉄則です。
登山における地図の読み方とは、現在地を読むということです。
現在地を読むとは、目の前にある地形と地図を照合させ現在地を把握すること。
的確に読むことができれば、コンパスがなくても90%以上の確率で現在地を把握することができます。
自分は今、地図上のどこにいるのか。
展望の利く縦走路ではさほど難しいものではありません。
しかし、低山や展望の利かない谷沿いの登山道などでは視野は限られ難しい作業になります。
そこに地図読みの奥深さがあり、そして楽しさがあります。
コンパスは、現在地確認作業において強力な証拠を示してくれ、また進むべき方向も示してくれるもの。
でも、間違った使い方をしてるとその精巧さは失われてしまいます。
人間は、方位を体で感じることができません。
コンパスはそれを補う道具であり、頼もしい相棒です。
それは、コンパスが指す方向確認の精巧さはピカイチだからです。
スマホでGPSを利用できる時代となり、登山者にとって安心して山の中に入れる時代になりました。
これで道迷い遭難者が随分と減るのではないかと期待していましたが、実際には減りませんでした。
でも、そんな便利な機能を使わないわけにはいきませんよね。
だけど、現在地を把握するだけ、あるいはルートを外したときに知らせを受けるなどといった「事後報告」を受けるだけの使用に意味は見いだせません。
そこには「先読み」がないからです。登山において重要なのは「先読み」だと思っています。