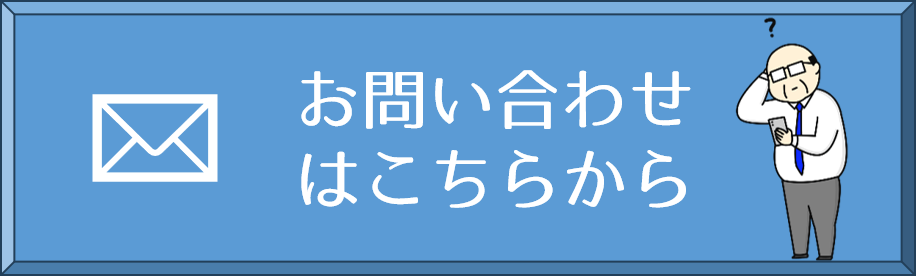5月頃の気候のいい日、山の中を歩いていてちょっとでも開けた場所にくると必ず彼らはいます。
ブンブン、ブンブンと音を鳴らしてホバリングしているハチです。
黒くてずんぐりと丸い体で小さな翅を羽ばたかせて、ドローンのようにホバリングしていたかと思うと急スピードで動きだす。あっちに飛んで行ったかと思うと、また戻ってきてホバリングしだす。
羽音が大きくてちょっと怖いけど、襲ってくる様子もない。
そんな彼らの正体は「クマバチ」というハチです。私が子どもの頃は「クマンバチ」と呼んでいました。
いつも出会う度に「ホバリングして何してるんだろう?」と思っていましたが、ちゃんとした理由があったんですね。

そう、それはメスを待っているのです。
そんな彼らにとって、飛んで近づいてくるものはメスか、自分の縄張りを奪いにきたオスのどちらか。
オスが来たのかメスが来たのか分からないので、近づいてきたものは追いかけなければいけません。
ちょっとかわいい話ですが、丸い石ころをクマバチに向かって投げると必死に追いかけていきます。
そして、ただの石ころだと気付くと、とぼとぼと自分の縄張りに戻ってきてホバリングを再開します。
なんだか愛嬌がありますよね。
私はこのことを知ってから、あのずんぐりむっくりのクマバチがとっても好きになりました。
そして、なんてかわいいやつなんだと。
時々、石ころを投げてはクマバチと戯れています。(←しちゃいけません)

そして、もう一つ。クマバチの毒針は卵を産むための産卵管が変化したもの。つまり、縄張りをはっている「オス」のクマバチは毒針を持っていないとのこと。
黒くてずんぐりしててホバリングするクマバチは、あまり怖がらなくてもいいのです。
ただ、メスは毒針を持っているので注意が必要です。
メスは顔全体が黒いなどの特徴がありますが、すぐに見分けることは難しいと思います。
なので、クマバチを見かけたら刺激せずに静かに見守ってあげましょう。
私みたいに戯れてはいけません。


メスの針はとても太いため、刺されるとかなり痛いとのこと。
しかし、毒性はほかのハチに比べると低いので、刺されても炎症がひどくなりにくいといわれています。
また、新型コロナワクチンで有名になった「アナフィラキシーショック」を起こす可能性も低いとされています。
ただ、ポイズンリムーバーはザックに入れておきましょう。刺されたらこれで毒を吸い取ります。このタイプが女性でも扱いやすいです。
毒液を吸い出したあとは、炎症反応を抑えるステロイド軟こうを塗ります。この商品は、かゆみ症状を抑える抗ヒスタミン剤含有です。
クマバチの生態
クマバチは、縄張り意識の強いハチ。
自分の縄張りを主張して人の周囲をブンブン飛び回りますが、本来はおとなしいハチと言われています。
飛んでいるだけなのであれば、静かに見守り刺激させないことが大切です。
樹木などの枯れ木や竹に穴を開け、そこを巣としています。そして、同じ巣を数年使い続けます。
ミツバチ科のハチのとおり、花の蜜や花粉を食料としていて特にフジの花が大好物。
藤棚には必ずといっていいほど彼らはいますよね?
そんなフジの花も、クマバチに来てもらわないと困ります。クマバチにこじ開けてもらって初めて花が開くのです。クマバチがいるからこそあの綺麗なフジの花が見られるということ。

そんなクマバチの寿命は約1年。
4月頃から飛び始め、中秋頃まで活動しています。
夏ごろに生まれた新しい成虫は、巣から出ることなく冬眠します。
女王蜂と働き蜂のような社会性を持つハチではなく、基本的には単独行動で親子としての関わりがあるのみです。
なんか、カッコイイな。
理論上飛ぶことができないハチ
あのかわいらしいずんぐりむっくりの体系に小さな羽。
多くの技術者たちに、理論上飛ぶことができない虫であるといわれていました。
しかし、そんなふうに言われていることも知らずに、ホバリングに空中アクロバット。
とにかく理論上不可能な曲芸を次々にやってのけます。
なぜなのか。
科学者や技術者たちが必死になって調べた結果、ある事実が判明しました。
それは、飛行機や鳥とはまったく違った原理で飛んでいるということです。
飛行機や鳥は、翼の上下の空気の流れの速さの違いを利用していますが、どうやら上手に渦を作ってそれを利用しているそうです。

もしかしたら、昆虫型の小さなドローンが、そのうち家の中を飛び回る時代が来るのかもしれませんね。
ブンブン、ブンブンと大きな音を鳴らして。