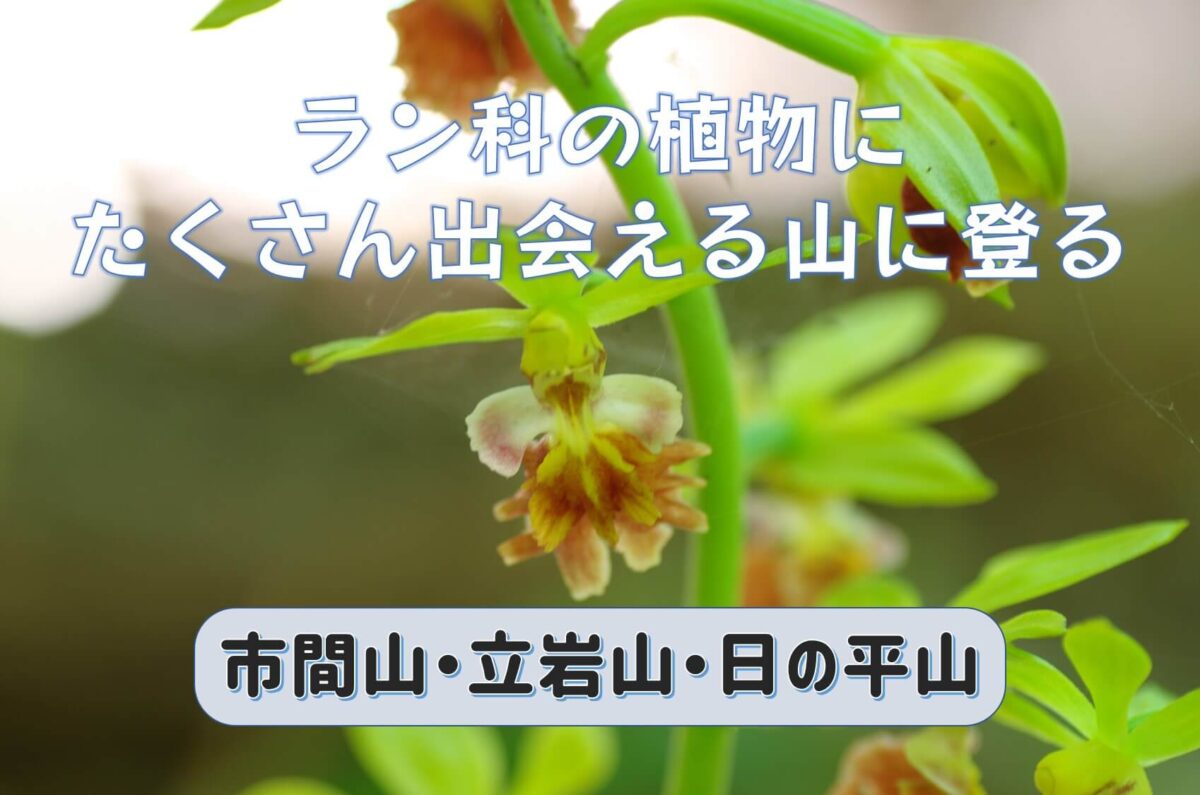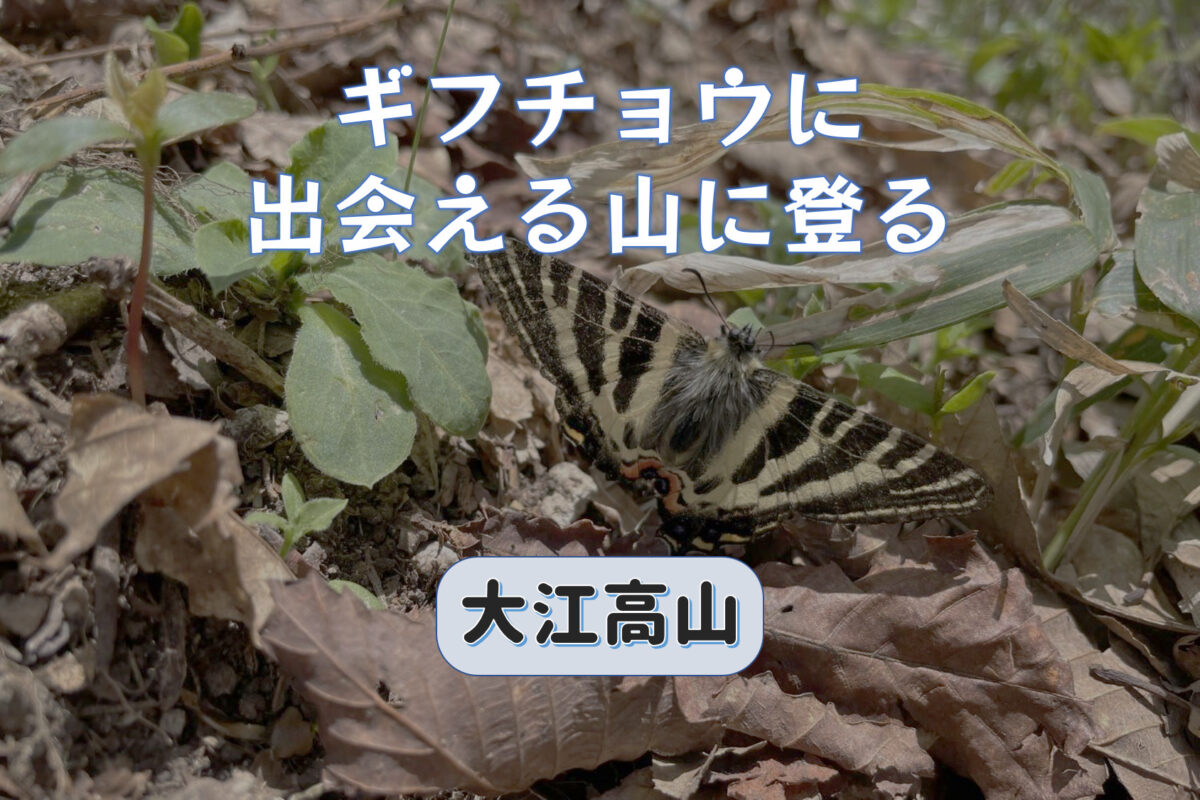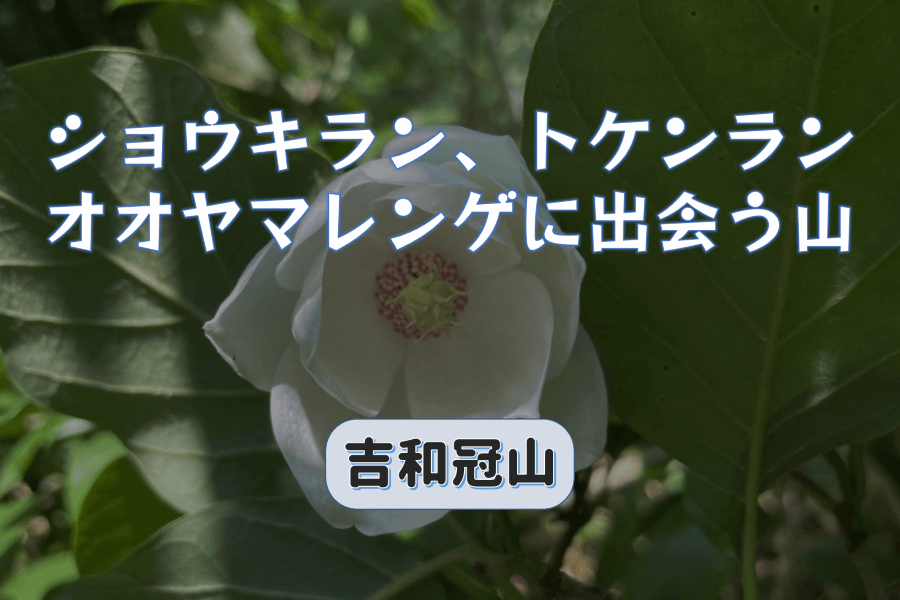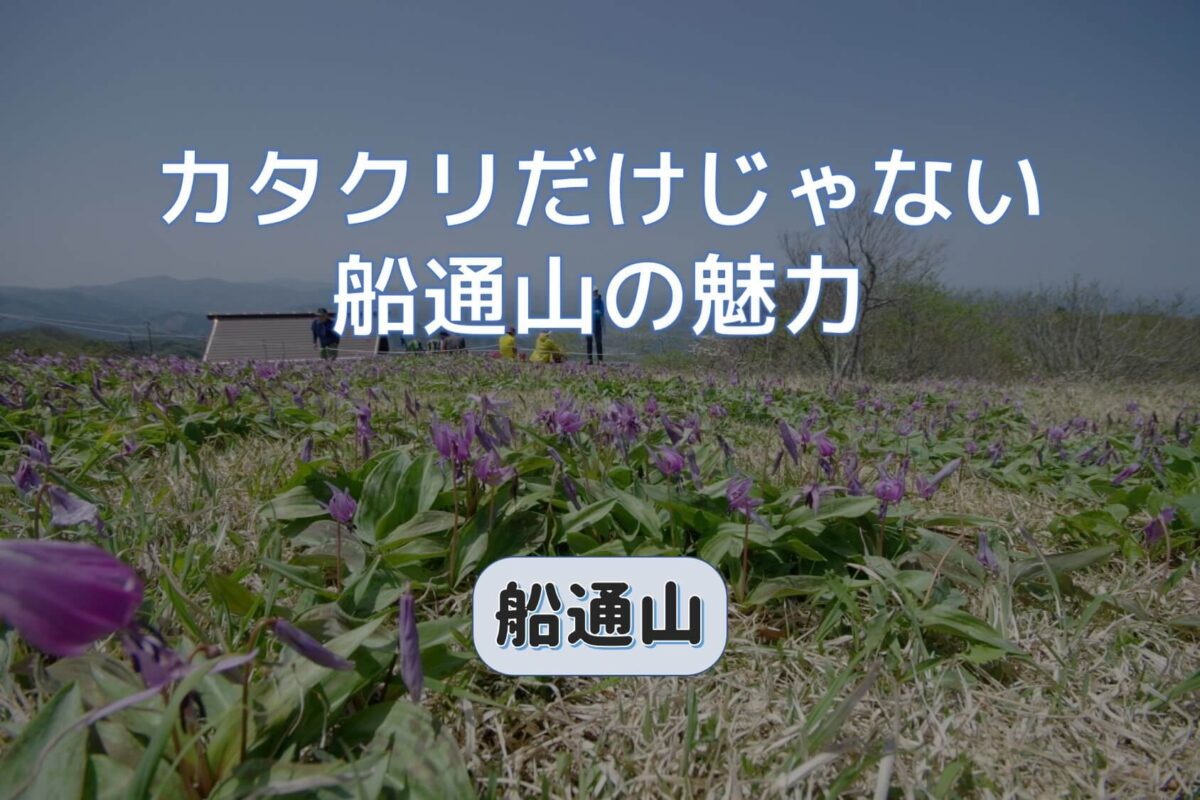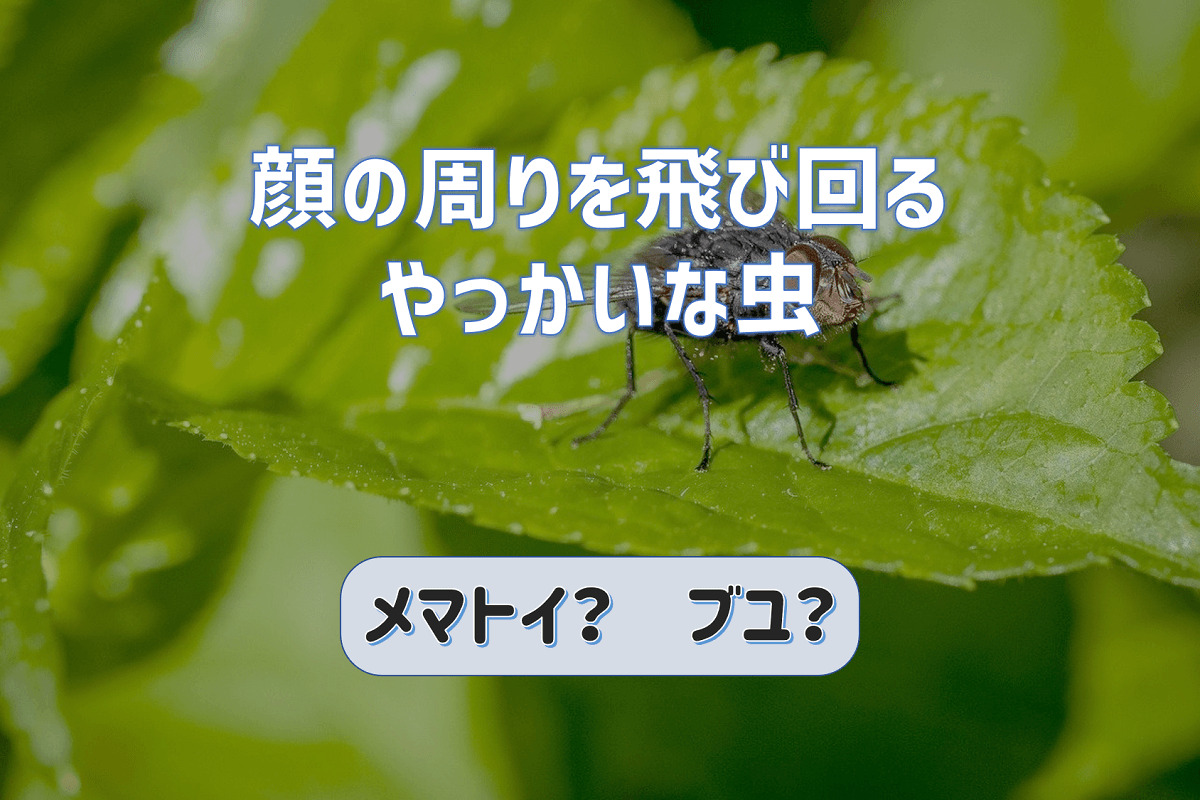登ってきた山、登山の危険性、登山ギアやウェア、地図読みについて記事にしています。
広島県の山を中心に、登ってきた山の一部を紹介しています。
年齢を重ねるたびに、登り方など少しずつ変わってきました。
若い時はがむしゃらになって登っていたけど、立ち止まって花を見たり、カメラを構えることが増えた気がしています。
ただ、若い時も今も、追い求めているものは変わっていないのかも。
きっと、まだ見たことのない景色を追い求めているだけのような気がします。
山に登ってみませんか?
どんなに便利な世の中になろうと、どんなにバーチャルな社会になろうと、目の前に広がる自然の景色で心が動かされます。
見てみませんか?
まだ見たことのない景色を。
感じてみませんか?
新しい自分を。
自然の美しさ、達成感や充実感、忙しい日常を忘れる、心身を鍛える、癒される。
山に登るという行為は何物にも代えがたい経験を私たちにもたらしてくれますが、これだけは伝えておかないといけません。
それは、山には様々な危険が潜んでいるということです。
ビギナーもベテランも関係ありません。自然は一瞬で命を奪います。
登山のいい面ばかりを取り上げる情報や、購買欲をそそる新しいギアやファッションとしてのウェアの情報などといった魅力的な情報は積極的に発信されています。
しかし、毎年多くの遭難者が発生し多くの命が失われていることを踏まえると、やはりネガティブな情報も発信し「山には危険が潜んでいる」という認識をもってもらうことが我々の責務であると考えています。
読図は、低山登山においては最も重要なスキルだと個人的には思っています。
ある程度高い山は、登山関係者が多く入山するためなのか迷うような踏み跡が少なく、道標もしっかり整備されています。
これが低山になると状況は一変。
林業や電力事業、地元の人たちが山に入ることが多く、その人たちが付ける明瞭な踏み跡が多く存在しているのです。
さらに、道標もあまり整備されていないために迷う分岐があちこちに。
そう、低山は道迷いのリスクが高いのです。
山での遭難事故の原因は、道迷いがダントツの1位です。
そのリスクを低減するためには、自分は地図上のどこにいて、どこに向かおうとしているのかを知っておくことが重要です。
それは、これから歩く道はどんな道で、次の現在地把握ポイントはどこかといった地図の先読みを繰り返しながら歩くことが重要です。
GPSで現在地の事後報告を受けながら歩くことではありません。
そして、道迷いを遭難に繋げないことが何よりも重要です。
道迷いは誰にでも起こりうるもの。その道迷いに気が付いたら、来た道を引き返すことが重要です。
道迷いに気が付いたとき、誰もが引き返す労力が大きいと勝手にバイアスが働きます。
「この道を引き返さないといけないのか」と誰もが引き返す労力の方が大きいと判断してしまうのです。
ある程度地図が読めるようになると、地図を見て「このまま進んでも大丈夫、ここに下山できる」「この谷を横切れば正規の登山道に戻れる」と考えてしまいます。引き返す労力より小さいと勝手に思い込んでいるのです。
その先に待ち受けるのが滑落や遭難です。首尾よく下山できたとしても、それは引き返すより大きな労力を払っていることでしょう。
道に迷ったと思ったら、来た道を引き返す。これが鉄則です。