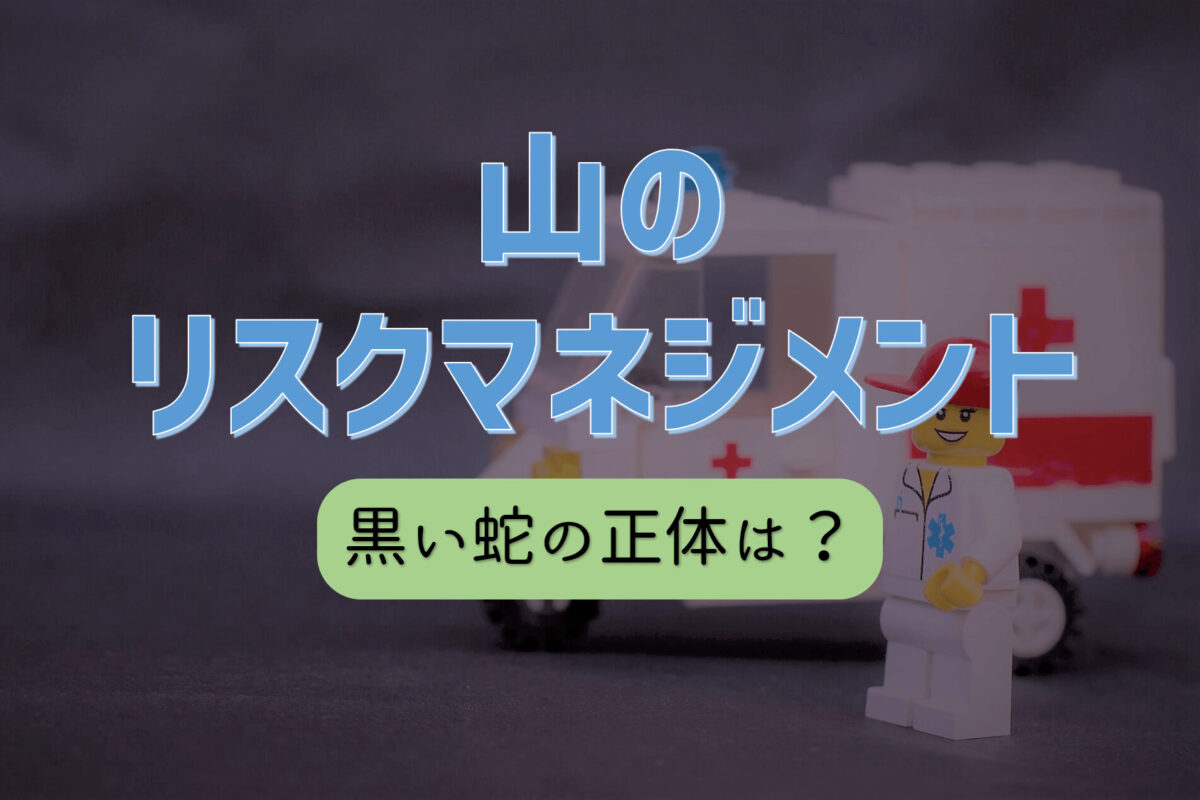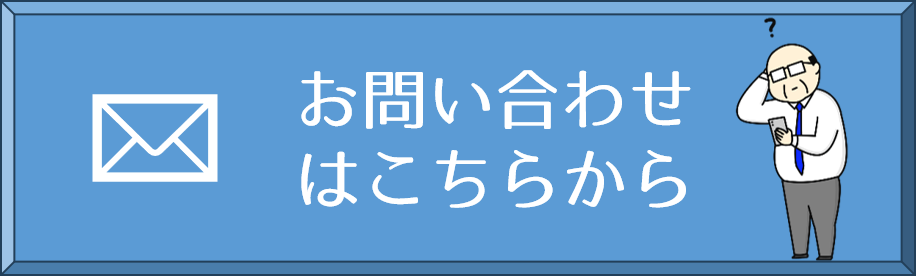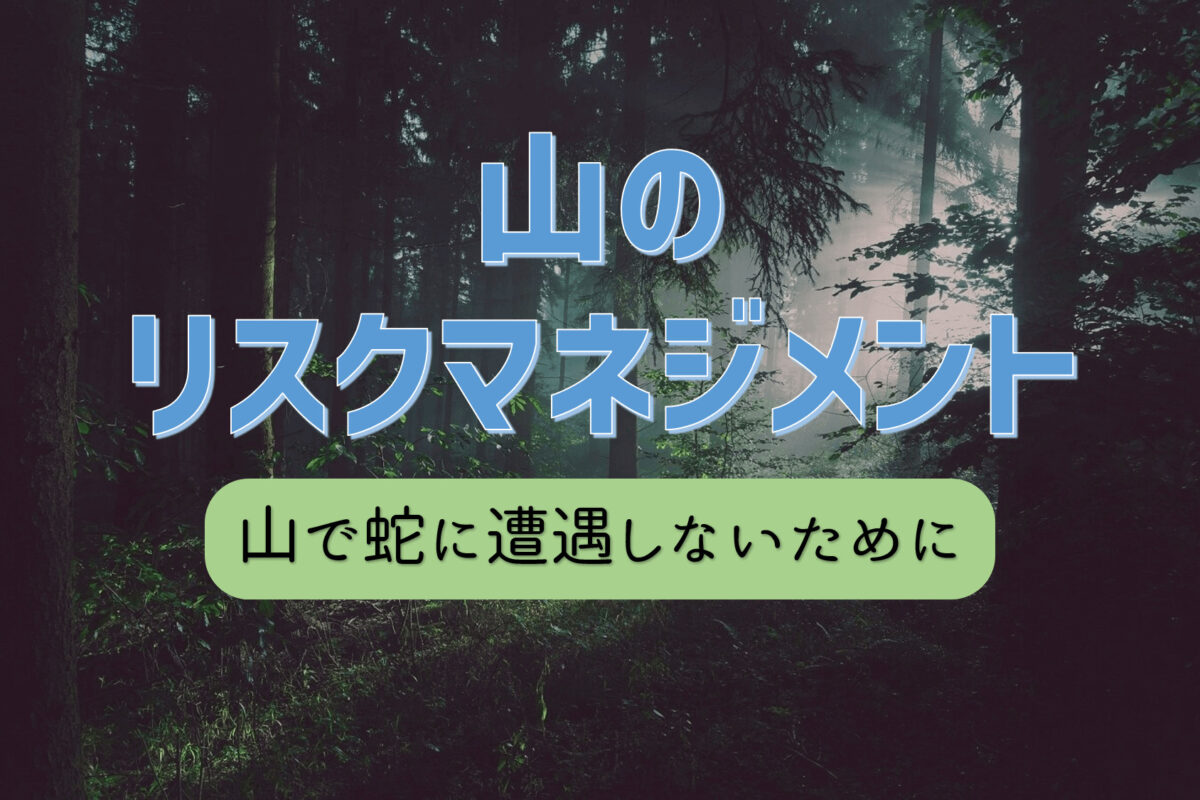
登山中に毒ヘビに遭遇しないためには、毒ヘビの特性を知ることが重要です。
といっても、夏場の登山道ではマムシによく遭遇しますよね?
夏の中国山地の山では、マムシを捕まえるために山に登っている人もいるぐらい・・・
一匹数万円で売れるそうです。
夏場の山で彼らに遭遇しないことは基本的に不可能です。
なので、重要なのは遭遇してもかまれないようにすること。
人間の方から刺激しないかぎり、ヘビの方から攻撃してくることはまずありません。(ハブは別です)
ヘビは自分で体温調節ができない変温動物なので、外の温度に影響を受けます。なので、ヘビは寒い時期は冬眠していて、活動期は暖かい4-10月です。なお、かまれる被害が多いのは7~9月です。
よって、この時期に山行する場合は、ヘビに遭遇するものとして考えておく必要があります。
山で注意すべきはマムシとヤマカガシ
日本にいる毒ヘビは、北海道から九州にいるマムシ、本州から四国、九州にいるヤマカガシ、そして、沖縄と奄美諸島にいるハブです。
沖縄や奄美諸島の山には登る機会が少ないでしょうから、山歩きで注意すべきヘビはマムシとヤマカガシと言えます。
マムシ

体長40~60cmの太くて短いずんぐりとしたヘビです。
頭部が三角形で体にある銭形斑紋を見て「あ!マムシだ!」と分かりやすいですが、体の色は茶系・黒系・赤系と体色変異が大きいです。
ただ、マムシは保護色であることから山では気づきにくいです。
落ち葉や土と同じような色のため、近くまで行かないとマムシに気がつかないですよね?
近づいたときにヘビの方がニュルニュルと逃げて、「あ~ヘビがいたんだ」と初めて気付くことが多いです。(→個人的にはヘビが苦手なので、飛び上がるくらいビックリしていますが・・・)
逃げてくれればいいですが、マムシは人が近づいても逃げないことが多いです。
どれだけ音を立てても逃げようともしません。(ヘビは絶対気付いている。と思う)
そんな時、登山道が広ければいいですが、狭いとどうしようかと悩みます。つんつんしたいのをぐっとこらえて、大きく迂回したことが何度もあります。
マムシは地面や岩場にいることが多く、木の上から襲ってくることはまずありません。水辺を好みますが、寒さに弱いため、寒冷地に生息することはまれなケースと言われています。
標高の高い山には生息していないのでしょうね。
そして、知っている人も多いと思いますが、マムシは他の日本のヘビと違って、卵を産むのではなく小さな赤ちゃんマムシを産みます。卵を体内で孵化させてから産んでいるのです。その数2~15匹。
交尾は夏の終わりにして、1年後の晩夏から秋にかけて出産しています。
春から夏にかけてはほぼ夜行性で、昼間は日光浴に登山道や岩場に出てくるくらいで夜に餌を探し回っています。
しかし夏になると、妊娠中のメスが胎児の成長のために盛んに日光浴を行い、昼夜の区別なく餌を探して栄養を蓄えて出産に備えます。
そのために日中でも人間がマムシと出会う回数が多くなるのです。
そして、マムシの毒はハブよりも強いと言われています。
ただ、注入量が少ないため死亡事故は非常に少ないです。咬まれた人の約1%が死亡すると言われていますが、被害を届ける義務がないために国や県も正確な件数は把握していません。
なお、アオダイショウの子どもも体に模様があって、これがマムシに似ていることからよく間違います。
山の中では突然遭遇することがほとんどなので、とっさには判別できないです。
アオダイショウは無毒で遭遇しても問題ないのですが、私にとってはどっちも遭遇するとかなりビビるので嫌です。

ヤマカガシ

全長1mほど。体の側面に黒斑が並び、若い個体は写真のように体の前半部に赤斑が混じり、首筋が黄色いです。
こちらも体色は個体によってかなり差があります。体色が真っ黒だと黒斑も目立たないので、まず分かりません。
ヤマカガシは水辺など湿った所を好む傾向がありますが、尾根道でも時々見かけます。
ただ、個人的にはマムシより遭遇率は低いかな。
ヤマカガシはマムシと違って昼行性です。
マムシもヤマカガシもおとなしい性格
マムシとヤマカガシはおとなしいヘビで、人間から手を出しさえしなければ、向こうから襲ってくることはまずありません。(→ハブは攻撃的で近くを通りかかっただけで飛びかかってきます)
ヤマカガシはマムシより臆病だそうで、人が近づいてくると逃げてしまうとのこと。(→だから遭遇率が低いのかも)
咬まれるのはヘビを捕まえようとして手を出したときや落ち葉の陰などにいて、ヘビがいることに気付かずに手を出して咬まれることが多いです。
また、草むらでうっかりヘビを踏んでしまった時などにかまれることも多いみたいです。
咬まれたら
マムシに咬まれた場合、直後から咬まれた部分の痛みが発生し、30分ほどで腫れが出てきます。
皮下出血や水疱が出ることもあります。逆に咬まれてから1時間以上経っても腫れていない場合は、毒ヘビでなかったか、毒ヘビだったが毒が注入されなかったことになります。
症状が進むと頭痛やめまい、嘔吐などの症状や、視力低下などの目の症状が出ることも。
ヤマカガシは溶血性の毒を持っていて、かまれてから数時間たってから、傷口から出血し、歯茎や皮下、内臓、粘膜からも出血します。
あと、首筋にも毒を出すところがあって、首をつかんだ時に毒液を飛ばしてくることがあるそうです。
子どもの時、友達がヘビを捕まえてブンブン振り回してましたが、ヤマカガシだったらやばかったですね。
1.まずは落ち着いて安静にし、急いで医療機関へ
動き回らず安静にします。すぐに呼吸が止まってしまうことはないので、まずはあわてないことです。
激しい運動をしてはいけないと言われていますが、登山は下山でも激しい運動になります。ゆっくり下山し、急いで医療機関へ行きましょう。救急車を呼んでもいいレベルです。
ヘビに咬まれたあと、患者本人が虫刺されと誤認したり軽症と判断したために来院までに時間が経過して処置が遅れることがあります。
噛まれた後すぐに顕著な症状がなくても、3~4時間後に重篤な症状をおこしてくることがあるので、必ず早期に医療機関を受診することが必要です。
マムシに咬まれた部分は腫れることが多く、放置しておくと腫れのために腕の中の圧が上がり、血管や神経、筋肉が損傷してコンパートメント症候群という状態に。
必ず受診しましょうね。
2.傷口を洗浄しよう
ヘビに咬まれた場合、野生のヘビの中には当然多くの菌や寄生虫がいますので、傷口をしっかり洗浄する必要があります。
特にヘビの歯は生え替わりが多く、歯が傷口に残ると化膿することもあるため注意が必要です。
3.口での吸引や縛る処置は行わない方向に
マムシの可能性があれば腫れてくるので指輪や腕時計を外しましょう。
以前は毒を吸引したり咬まれた腕を心臓に近い側で縛ったり、という処置がされていましたが、最近はこれらの処置はしない方向にあります。
ヘビ毒の吸収は早いため、吸引したところでたいして回収できないからです。
もっともやってはいけないわけではなく、こんな吸引機で吸引したり指で強くつまんで毒を絞り出すことはしてもかまいません。
口での吸引は、救助者の口の中に毒液が触れる可能性もあり、お勧めできません。
ただ、吸引でどれだけ重症化予防できるかは不明とされています。
予防策
夏場の登山は、必ずマムシやヤマカガシに遭遇するものとして意識する必要があります。
遭遇する確率は高いものの刺激しないかぎりかまれる確率は低いので、刺激しないことが重要です。
次の4つのことを頭に入れて山に登りましょう。
①マムシもヤマカガシも水辺などの湿った所を好むため、沢沿いの登山道を歩くときは注意が必要。
②ヘビの活動期に草むらやヤブといった足元の視界が悪い場所を歩くときは、特に注意が必要。
③手をついて岩場を登るようなときは、一層の注意が必要。(→足は登山靴で守られているが、手は無防備なことが多い)
④マムシもヤマカガシもおとなしい性格で、人間から刺激しないかぎりまず襲ってこない。
昔から蛇は「神の使い」といわれています。
見つけても子どもの時のように「わ~い! わ~い! ヘビみっけ! つんつん!」
なんて、枝やトレッキングポールでつんつんしないようにしましょうね。