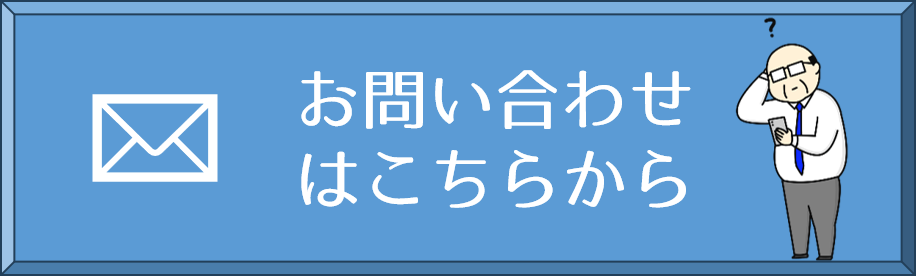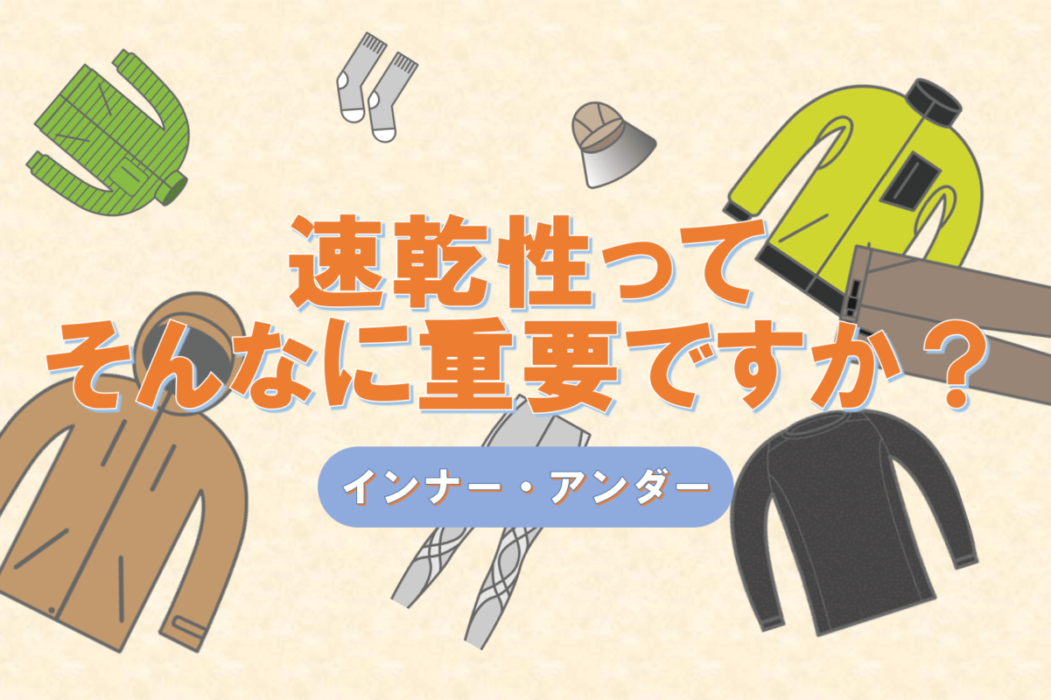
登山ウェアの中で最も重要となるウェアは、Tシャツやアンダーなどの「インナーウェア(ベースレイヤー)」です。
それは、脱いだり着たりができないウェアでありながら、同時に体温を適切に保つことが求められているからです。
一般的に求められてる機能としてよく挙げられるのが、「吸水(吸汗)速乾性」です。
かいた汗を素早く吸収し、すぐに乾燥させて汗冷えを防ぐ吸汗速乾性が重要であると多くの人が言っています。
本当にそうなのでしょうか?
真冬の寒い時期の登山に、速乾性のインナーが本当に必要と思ってるのでしょうか?
早く乾くということは、そのぶん気化熱で暖かさも一気に奪うので体は冷えるという現実を知っているのでしょうか...
それは、体温を適切に保ち安全な登山とするために適切な情報となっているのか。
いつも疑問に思ってます。
ポリエステルの吸水性
そもそもポリエステルの繊維自体は、水分を吸水しません。繊維自体は「疎水性」です。
繊維が水分を吸わないので速乾性に優れているというわけです。
では、なぜ世の中のポリエステルの商品は「吸水・吸汗」を謳うのか。
それは、後加工として親水性に優れた加工剤を塗布しているからです。
しかし、これでは洗濯を重ねることで、その効力は少しずつ落ちていきます。
酷いものでは、ポリエステルを使用しているだけで吸水速乾(実際には水は全然吸わない)を謳って売られているものもあるので注意が必要です。
それとは別に登山用ウェアなどは、繊維の形状を工夫するなどして水分を生地表面にすばやく薄く広がらせ、空気に触れる表面積を増やすことで速乾の機能を向上させています。
いわゆる毛細管現象を発現させて水分の移動を促進させているのです。
繊維自体が水分(汗)を吸収しているのではなく、水分をすばやく吸い上げ(移動させ)て生地表面に拡散させているのです。
生地表面に拡散された水分は、生地内外の温度差、湿度差や風によって蒸発し、結果として肌の汗が除去されます。これが化繊の汗処理の工程です。
こうした高機能繊維として使われているポリエステルと、汎用のポリエステルでは吸水性は異なるということを頭に置いておく必要があります。
登山用のウェアの値段は高いですけど、こうした工夫がされている高機能繊維であるがゆえに「お高い商品」となっているわけです。
購入の際には、こうした工夫を調べることがポイントです。
大量の汗をかくときのインナー
大量の汗をかくときのインナーに求められる機能は、クールダウンの「速乾性」です。
それは、ゆっくり乾くインナーでは、乾くのが追い付かないからです。
本来は、汗をかけば汗が蒸発する気化熱で体温が下がるところを、濡れた服を着ていることで汗が蒸発せずに体に熱がこもってしまいます。
よって、熱を内側にこもらせないために吸汗、拡散、速乾に優れたウェアでクールダウンさせることがポイントになります。
保温とクールダウンとの境界が難しいですが、大量の汗をかくときは汗処理と体温を上げないクールダウンを優先させたほうがいいのではと思っています。
登山用ウェアは、一般的なスポーツウェアより、いわゆる吸水拡散性に優れ、速乾性も勝っています。
値段が高いだけ、その意味はあるということです。

大量の汗をかかないときのインナー
大量の汗をかかないときに求められる機能は、体温維持の「ゆっくり乾く」ことです。
ただし、一般的には綿製品もゆっくりと乾きますが、大事なのは、肌に触れる部分が濡れているかどうかです。
吸い上げた水分をゆっくりと乾かすことで、急激な蒸発で体温が奪われるのを防ぐのですが、肌に触れる部分が濡れていては、逆に体温が奪われ体温維持ができないからです。
皆さんも経験があると思いますが、濡れた綿製品を着ていると冷たいと感じます。
肌に触れる部分が濡れているからです。
なので、綿製品は吸水力があるものの登山には向いていないといわれる理由がここにあります。
綿も天然素材ですが、登山ウェアに多用される天然素材があります。
それはウール ![]() です。
です。
ウールは、繊維の表面は水を弾き、繊維の内部の層が湿気を吸収する「水をはじくが水を吸う」性質を持っています。
よって、羊毛繊維が濡れても、表面は疎水性で水をはじくことから、肌と直接触れ合うことがなく、冷たく感じることがないのです。
汗を含んだ状態でも体温を保つことができる素材なのです。
ウール製品は少々高くてすぐダメになる素材ですが、汗冷えを防ぎ体温を適切に保つことができる機能を持つ天然素材であるといえます。
よく、「速乾性に優れたものを着ましょう」と言いながら、メリノウールを紹介しているものが多く見られます。
メリノウールに速乾性はありません。緩やかに乾く天然素材です。

3~4時間の登山におけるインナーウェア
登って下りてくるまでの時間が3~4時間程度の低山登山の場合、気候がいい時期であれば、ぶっちゃけ何着てもいいと思います。(←個人の見解です)
ぶっちゃけ綿製品でもいいのではと思ってます。
綿製品は極端ですが、安い化学繊維の服でもいいと思ってます。
それは、1~2時間も歩けば下山口へ下りられる標高の低い山だからです。
少々汗冷えしても気候がいい時期の低山であれば、それを汗冷えと感じることは少ないです。
ユニクロやワークマンにあるポリエステルの商品でも十分なのかもしれません。
ただし、真夏の大量の汗をかくときの登山はちょっと注意が必要です。
それは大量の汗をかくことで、熱中症になる危険があるからです。
本来は汗をかけば汗が蒸発する気化熱で体温が下がるところを、濡れた服を着ていることで汗が蒸発せずに体に熱がこもってしまいクールダウンができません。
体温を下げる機能が追いつかない状況になると熱中症になる危険があります。重度の熱中症の場合、死にいたることもあるので注意が必要です。
よって、3~4時間の登山でも大量の汗をかく登山のときは、先に述べたことと同じようにクールダウンを目的に吸汗、拡散、速乾に優れたウェアを着る必要があります。
また、何年も着続けて、そして洗濯を何回も重ねた結果、吸水性が損なわれていることに気付かずに未だに着続けることは悲しいです。
あるいは、「最近吸水性落ちちゃったな~」と気付きながらも着続けることも悲しいです。
レイヤリング時の注意事項
ベースレイヤーを2つに分けて、1stレイヤー、2stレイヤーにしている人もいると思います。
吸水速乾性のあるアンダーウェアの上に、吸水速乾性のあるTシャツを着るなどです。
また、ベースレイヤーの上に防風に優れたジャケット(レインウェア)などを着ることもあると思います。
ポリエステルの乾く原理は、繊維自体に吸水させているのではなく、生地表面に拡散させて生地内外の温度差・湿度差や風によって蒸発させているといいました。
なので、ベースレイヤー(1stレイヤー)の上にピチッと体にフィットした通気性のないシャツを着ると、ベースレイヤーは風にあたることがなくなるので、理論上は乾くスピードが極端に落ちるということになります。
1stレイヤーに吸水速乾性のあるものを着た場合、2stレイヤーは通気性があって、ちょっとダブっとしたものを着たほうがいいということです。
ただし、生地内外で温度差も湿度差もなく無風の場合は、なかなか蒸発してくれません。
逆の発想で、2stレイヤーに吸水速乾性のあるものを着る場合は、1stレイヤーには汗をかいても肌に戻らず、肌から汗を素早く遠ざけてくれるようなものがいいです。
例えば、下記のような商品です。
また、透湿性のないジャケット(レインウェア)などを上に着た場合も、ベースレイヤー(1stレイヤー)が蒸発させた汗(水分)がジャケットで遮断されて外へ逃げていかないので、注意が必要です。
透湿性のないジャケットを着る場合は、通気性のあるものを着たほうがいいです。
つまり、吸水速乾性のある服をベースレイヤー(1stレイヤー)に着るのであれば、その上に着るものは少し考えて着ましょうということです。
保温性
山は標高が100m上がるごとに、気温が0.6℃下がります。
実は最も重要なポイントがこの保温性の機能であると考えています。
大量の汗をかくときの登山は、保温性よりもクールダウンを優先すべきですが、それ以外の登山であると保温性を最優先すべきです。
それは、計算上、2000mの山では気温が12℃も下がることになるからです。
夏でも、山の上はそこそこ寒さを感じます。
そして、運動強度が高くない状態で風に吹かれたりすることが登山では多いので、体温維持が重要になります。
つまり、吸汗して拡散して発散することより、汗を含んだ状態でも体温を保つことを優先すべきなのです。
メリノウールが最強と思われますが、ポリエステルの製品でもさまざまな工夫を施して保温力を持たせています。

まとめ
最も体温を下げる原因となるのは「自分がかいた汗」です。
大量の汗をかくときは、体温維持より吸汗、拡散、速乾に優れた機能でクールダウンさせる。
それ以外のときは、緩やかに乾き、汗を含んだ状態でも保温性のある製品。
ということになります。
また、インナーウェアは立派なんだけど、何も考えずにその上に着るものを選んでいても、その機能は十分に発揮されていないことになります。
ただ、インナーウェアで悩むより、道迷いによる遭難が毎年多く報告されていることから、どうすれば道迷いを防げるかで悩むほうが意味があるのではと思います。