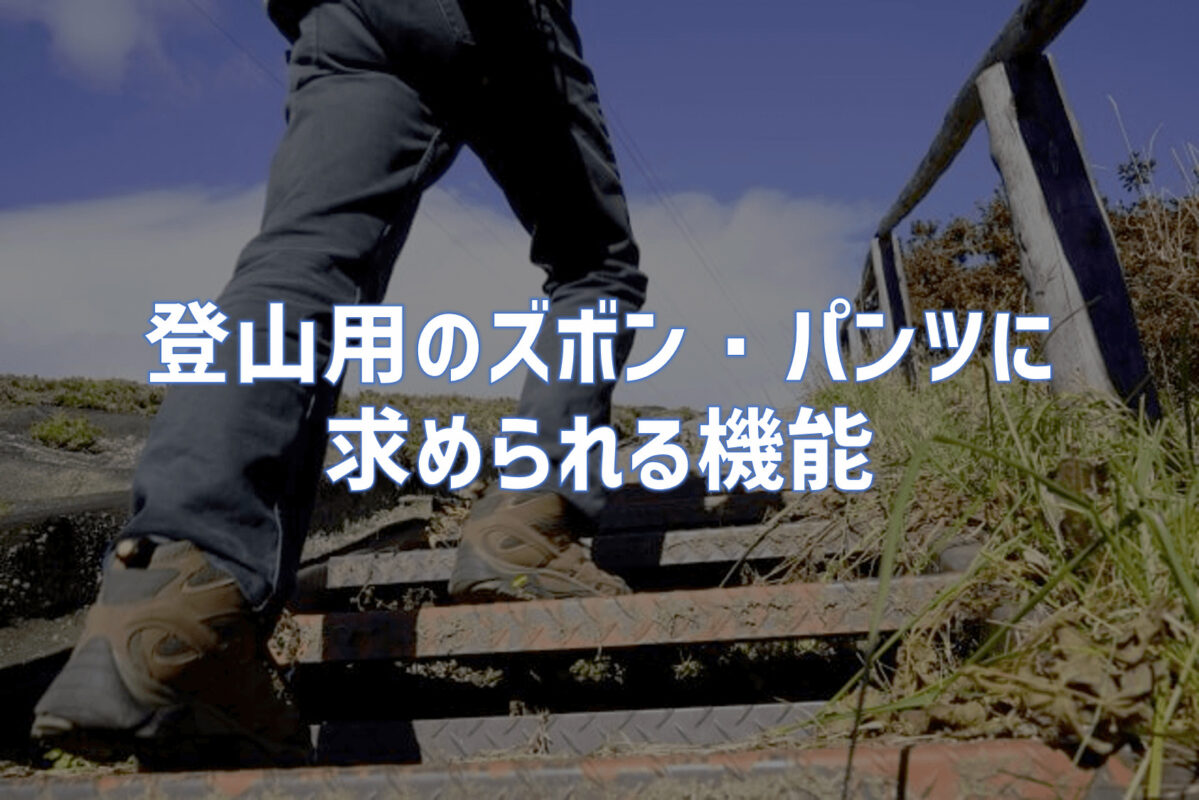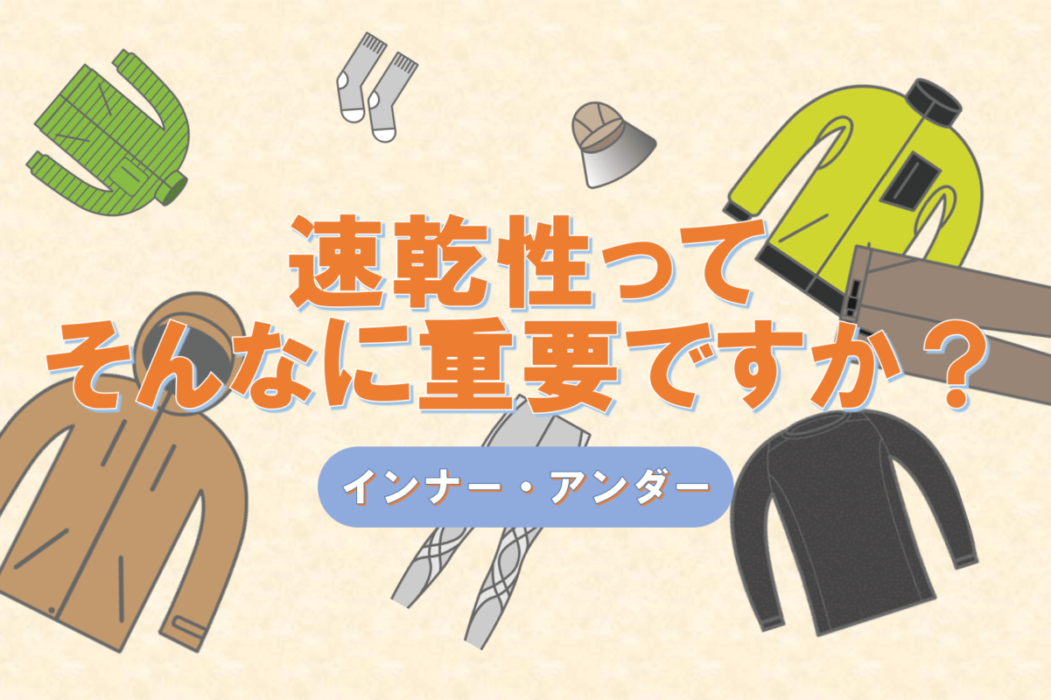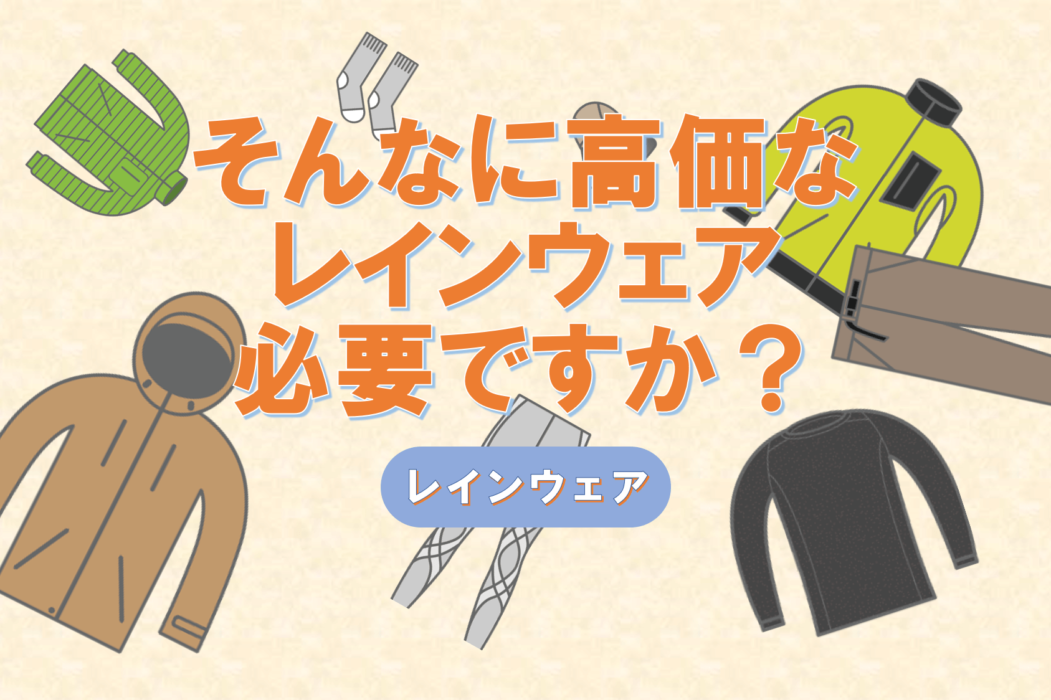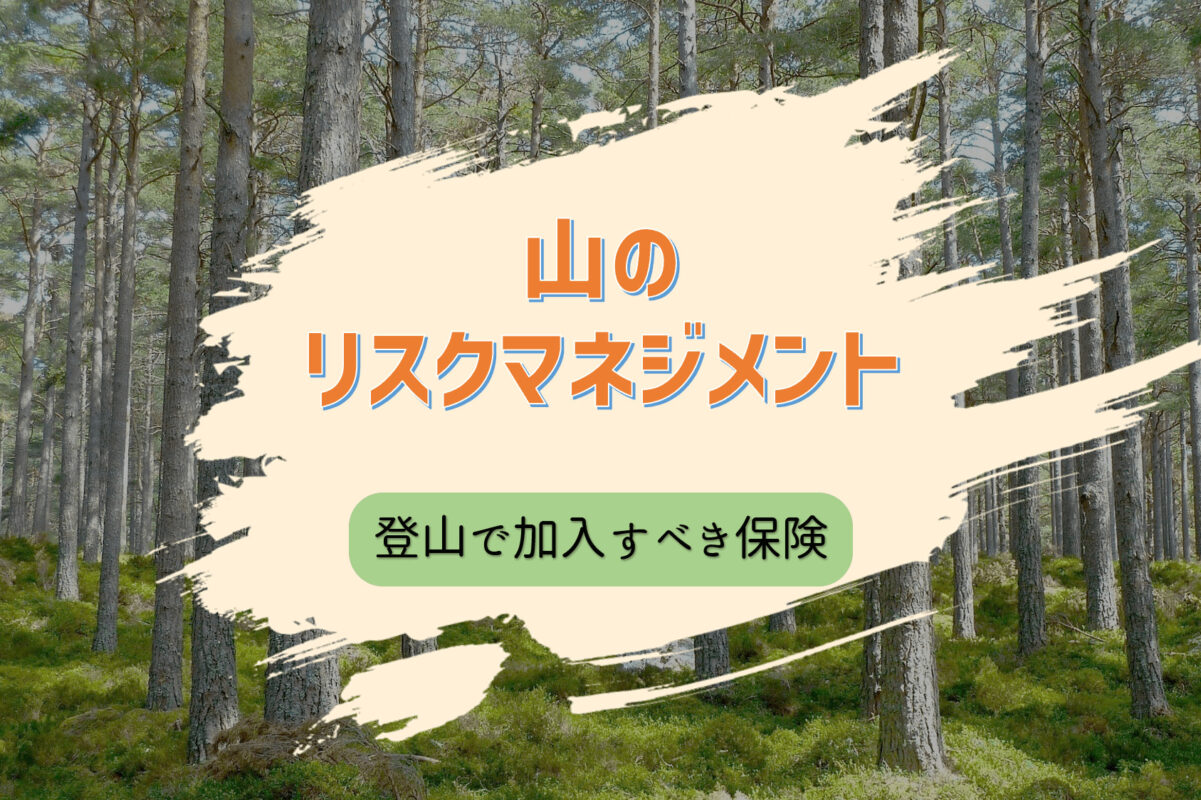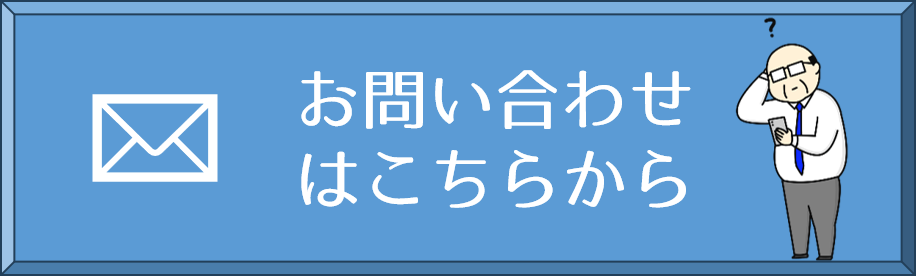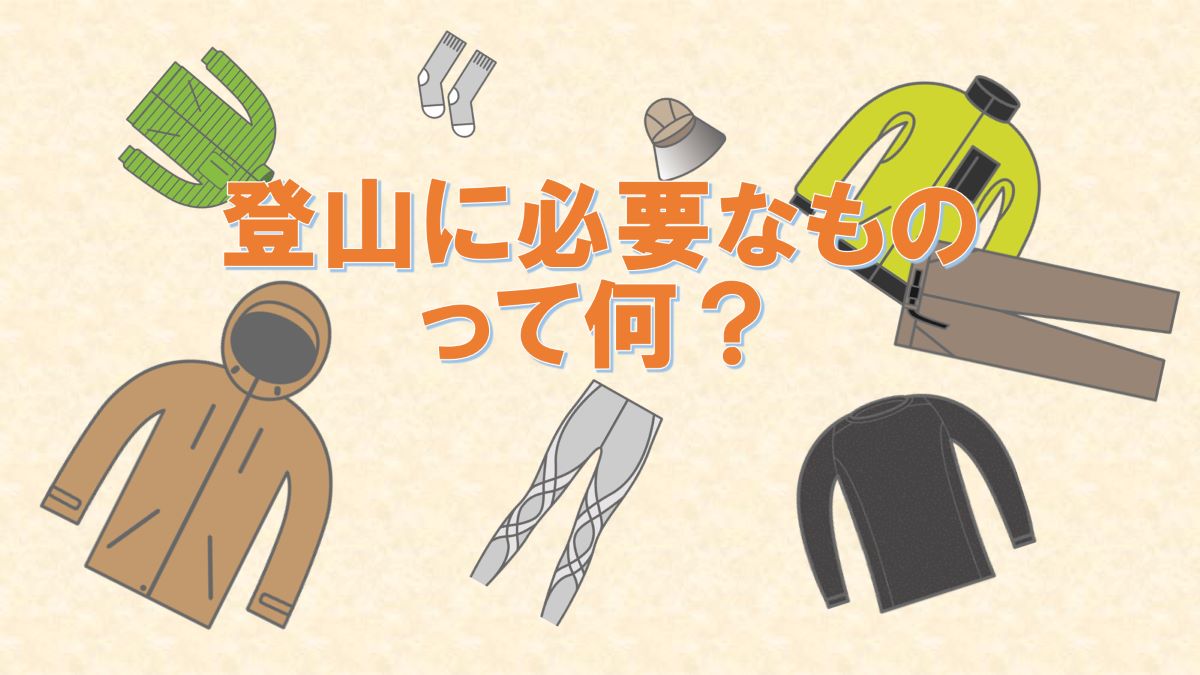
登山界で、一般的にいわれている登山の基本装備や必要な持ち物。
登山靴、登山ウェア、レインウェア、登山ザック、ヘッドランプ、地図とコンパスetc、、、。
これらは「登山するのであれば必ず揃えましょう」と言われています。
それは『安全に登山するために、少しでもリスクを減らしましょう』が根本にあるからです。
- ソール(靴底)
凹凸があって厚くて硬いのは、路面のデコボコなどに直接的に影響を受けず、鋭利なものから足を守ってくれて、滑りにくい。 - アッパー(靴底を除いた上の部分)
衝撃から足を保護し、歩いても足が踊らないよう絶えず足をフィットさせてくれ、水の侵入を防ぎ、内部からの湿気を放出してくれる。
体温を維持してくれて、快適な運動性を確保してくれて、長時間の運動にも耐えてくれる。
山に入るという行為は、時には牙を向く自然と向き合う行為。登山は、常に危険と背中合わせの状態になります。
そんな危険域にさらされる身を、少しでも安全域に近づけてくれるものたちなのです。
登山は、山に登ることが目的であっても最終目標ではありません。
最終目標は『無事に家に帰ってくること』です。
でも、登山用品はどれも高価ですよね。一度に揃えるとなると結構な出費になります。
登山靴やレインウェア、ザックについてはレンタルすることもできますが、それでも高価です。(←私はまず面倒だと思ってしまう)
まあ、普段登山しない人が「今年の夏は富士山登るぞー」って、富士登山する場合はレンタルがいいのでしょうけど。
なので、最初のうちは『山によく登っている人に連れていってもらう』ようにしましょう。
近所の街に近い標高差のない山で、登山口から下山口まで2~3時間で済む山にです。
山岳会に入ったりイベントに参加したりもありですが、最初のうちは身近な人に頼むほうがいいです。
いない場合はガイドを探したほうが無難です。
ただ、低山のほうが道迷いなどのリスクが高くなるため、きちんと次のことを伝えてください。
それは「あなたがよく登っている山で、私が今持っている装備でも登れる山に連れていってほしい」と。
さらに「雨なら中止にしてほしい」と。
それで少しはリスクが減ります。
「ジーパンしかない、綿のTシャツしかない、スニーカーしかない、普通のリュックサックしかないけど、それでも登れる山に連れていけ」と。
その格好で登ると、なぜこういったものがNGといわれているのかがよく分かると思います。
ただ、ケガや危険な虫や植物、脱水やシャリバテに対しては自分で予防するしかありません。
- 水(多めに)
- エネルギー源(飴玉やチョコでもいい)
- 汗拭きタオル
- 帽子と手袋
- 綿の服しかなくても長袖長ズボン
- 靴底が平ではないスニーカー・運動靴
- 両肩ベルトのリュックサック
- 健康保険証
- 緊急連絡先を書いた紙
気になる方は目かくしも
この中では、スニーカーでも靴底が平らなものしか持っていない人も多いと思います。
その場合でもきちんと伝えましょう。
「靴底が平らなものしか持っていない」と。
そうすれば、いくらかは滑りにくいような山に連れていってくれます。
そして、登った後にこれからも山に登りたいと思ったのであれば、まずは『登山靴』と『インナーウェア(ベースレイヤー)』だけでも買いましょう。あとは、少しずつ買い揃えていけばいいです。

まずは登山靴を買いましょう
これからも山に登ってみたいと思ったなら、まずは登山靴を買いましょう。
登山靴は、登山するのに最も重要なアイテムだと思っています。
それは、何時間もデコボコな道を歩かないといけないからです。
といっても、登山用品店へ行っても種類が多くて値段も幅があります。
アッパー(靴底を除いた上の部分)の高さは3種類
- ローカット:くるぶしが完全に出る
- ミッドカット:くるぶしあたりまで→メーカーによってはハイカットに見えてもミッドカットの名で売られているものもある
- ハイカット:くるぶしを完全に覆う
ソール(靴底)の硬さは大まかに3種類
- ガチガチに硬い(つま先と踵部を両手で掴んでひねったり力を加えてもびくともしない)
- そこそこ硬い(少しだけ曲がる)
- 柔らかい(スニーカーのようにふにゃふにゃ)
なので、お店の人に聞いて、実際に履いてみて自分の足にフィットするか必ず確かめましょう。
確かめずにネット通販で買うと、失敗する確率が高いです。
そして、聞く時は、どんな登山スタイルの靴が欲しいのかを確立させておきましょう。
例えば『日帰りで樹林帯が多い低山に登るための登山靴』とか。
とはいうものの登山靴は高くて何足も買えないし、将来的にはアルプス行って山小屋泊なんかもするかもしれない。
と思うのであれば、『ハイカットまたはミッドカットでソールがそこそこ硬いもの』がおすすめです。
日帰りで樹林帯の多い低山しか行かないのであれば、『ローカットまたはミッドカットでソールが軟らかい』もので十分です。
ローカットの靴であれば、普段でも履けて雨の日は重宝します。
詳しくは下記の記事で。
次に買うのは登山用ズボン・パンツ
登山靴を買ったら、次はズボン・パンツを買いましょう。
何時間も足を動かさないといけないので、運動性と耐久性重視で選びましょう。
これもお店ではいてみることがおすすめです。
詳しくは下記の記事で。
ただ、学生時代の体操着(いわゆるジャージ)があれば当分はそれで十分かもしれません。
その次はインナーウェアです
登山靴と登山用ズボン・パンツを揃えたなら、次に買うべきはTシャツなど肌の上に着るインナーウェア(ベースレイヤー)です。
その目的は体温維持のためです。
脱いだり着たりができないウェアでありながら、同時に体温を適切に保つことが求められているからで、寒さ・暑さから体温を守り、運動中の体温上昇や汗冷えを防ぐことを目的としています。
一般的には『吸水(吸汗)速乾性に優れたポリエステル繊維の服』と言われていますが、寒い時期は逆にデメリットになったりもしますので、詳しくは下記の記事で。
ただ、気候が丁度いい時期で2~3時間の登山なら、ぶっちゃけ安い化繊の服でもいいと思っています。
ザック、レインウェアは必要になったらでいい
基本的には雨の日に山に行くことは少ないです。
普通は「明日は雨だから登山は止めとこ―」となりますが、そうはいかない場合も出てきます。
なので、雨の日、あるいは雨が降りそうな日でも山の中を歩くようになったらレインウェアが必要です。
雨の日には絶対に行かないのであれば、無理して買う必要はありません。
詳しくは下記の記事で。
低山で、気候のいい時期の日帰りならポンチョでもいいです。
ザックも必要性を感じたらでいいと思います。
低山であれば普段使っているリュックサックでも十分ですし、腰ベルトなんてなくてもいいです。
買うのであれば、逆に普段でも使えそうなものを買うのもありです。
ただ、登山用ザックを背負ってるとカッコよく見えるので、形から入る人なら必須のアイテムなんでしょうね~
その他のもの
そのほかの物を買うようになれば、きっと登山にハマっている人でしょう。
もうこの記事は読んでないかもしれませんが、山岳保険は忘れずに入っておきましょう。
それでは、安全で快適な登山を楽しみましょう。